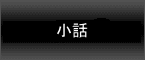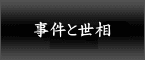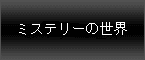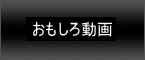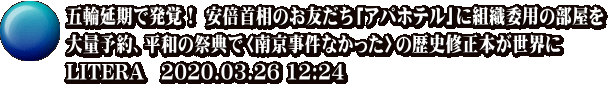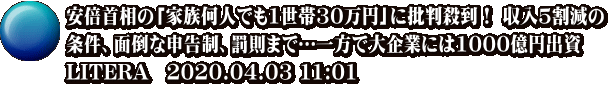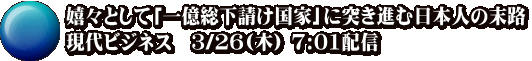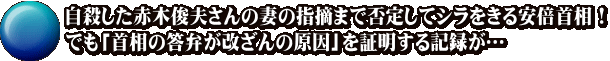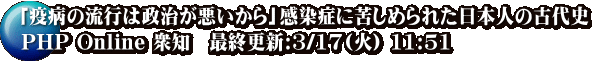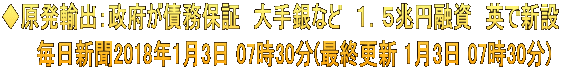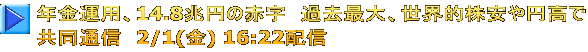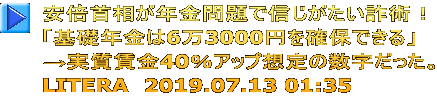|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
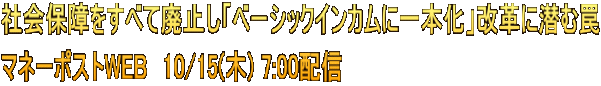 菅政権が発足したことで、ベーシックインカム(BI)導入論が高まっている。ベーシックインカムとは、政府がすべての個人に対して、生活に最低限必要な現金を無条件で毎月支給する制度である。
BI導入のきっかけとなったのは、菅義偉首相のブレーンで経済学者の竹中平蔵氏(パソナグループ会長)。コロナ禍では「究極のセーフティネットが必要だ」と、国民全員に“毎月7万円支給”を提案した。 しかし、国民全員に月7万円支給するためには、ざっと計算しても年間100兆円の財源が必要になる。竹中氏は、年金や生活保護などの社会保障を廃止し、社会保障財源をBIにあてる方法を提案している。今年8月に刊行した著書『ポストコロナの「日本改造計画」』でもこう書いている。 〈一人に毎月七万円給付する案は、年金や生活保護などの社会保障の廃止とバーターの話でもあります。国民全員に七万円を給付するなら、高齢者への年金や、生活保護者への費用をなくすことができます。それによって浮いた予算をこちらに回すのです〉 現在の年金制度について、安倍晋三・前首相は国会で「100年安心は変わっていない」と抜本的改革の必要はないと説明してきた。 その安倍政権の方針を踏襲すると宣言して政権を受け継いだ菅首相が、社会保障制度をすべて廃止してベーシックインカムに一本化するような乱暴としか思えない改革に走り出したのはなぜか。日経新聞は菅首相の政治手法に関する竹中氏の興味深い発言を報じている(9月28日付電子版)。 「民間人が政策会議などでトスをあげる。それを受けた菅さんが強烈なスパイクを政策として打ち込む」 「だがスパイクなので改革は点になりがち。これを面にしていく政策が今後必要になる」 実務家の菅首相は、個別の政策課題への対処はできるが、かつてあるインタビューに「正直言うとね、国家観というものがそれまでは私になかったんです」と語ったことがあるように、ビジョン作りは苦手のようだ。社会保障改革も、本当の司令塔は「トス」をあげるセッター役の竹中氏らブレーンたちで、首相は行き先もわからないまま、提案されるまま改革を推進していく。 その国民にとって危険な政権の意思決定の姿が、今回のベーシックインカム導入の動きの裏で浮かび上がってきた。 ブレーンたちが菅首相に急進的とも言える社会保障改革を実行させようとしているのは、それが今後のコロナ対策と、増え続ける社会保障費問題を一挙に解決する方法だからだ。 現在、コロナによる休業者数は全国220万人にのぼる。特例で延長されている政府の休業補償(雇用調整助成金)の期限が今年12月に切れれば、失業者となって町にあふれ、失業率はすぐに戦後最高の5.8%までハネ上がるとの試算がある。経済回復は遠い先の話で、事態はさらに悪化が予想される。そうなれば生活保護の申請が殺到し、社会不安が広がり、財源はパンクする。そこで社会保障財源の“流用”に目をつけた。 〈おそらく経済が本格的に回復するまでには、数年はかかるでしょう。もし一回限りの給付(編集部注・特別定額給付金の10万円)で終われば、それまでの長い期間に、生活破綻する人がどんどん増えてしまいます。そこで考えられるのが、国民一人当たり七万円程度を毎月給付するという案です〉(『ポストコロナの「日本改造計画」』より) 社会保障をベーシックインカムに統一して生活保護の代わりに国民全員に7万円配れば、当面のコロナ生活破綻は回避できる。 しかも、今後、国民の医療費や介護などの費用が膨れあがっても、政府は「100兆円」を配るだけで、あとは「自己責任だ」と新たな財源の心配をする必要はない。国民のセーフティネットを切り捨てることで、「増税なき財政再建」を実現しようという国家の陰謀である。国民はその対策を考えることが急務だ。 ※週刊ポスト2020年10月16・23日号
|
 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
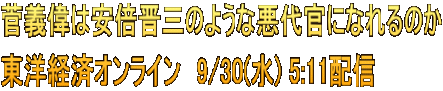 安倍晋三の長期政権が終わり、調整役だった菅義偉が首相となった。のっけから安倍政治の継承を掲げるという地味な路線での新政権スタートである。だが、この路線、長続きするだろうか。私は難しいとみる。 2012年末に始まった安倍政権の7年8カ月は、2016年央までの前期とそれ以降の後期に分けられる。 前期は異次元緩和の時代である。デフレの元凶とリフレ派から名指しされていた日本銀行、そこを制圧する占領軍司令官のような役柄で送り込まれた黒田東彦は、自ら異次元緩和と名付けた大規模な量的金融緩和策を打ち上げることによって安倍政権誕生に祝砲を放った。 この異次元緩和、人々の気分を変えたという意味では成功だったといえる。2008年のリーマンショック以来1万円前後で低迷していた日経平均株価は、安倍政権スタートとともに上昇を始め、2015年には2万円台を回復した。 安倍の経済政策、通称「アベノミクス」は、しょせんは金融緩和頼みと皮肉られながらも、ともかく緒戦で数字を出すことには成功したのである。 構図が変わったのは、日銀の量的緩和の限界が明らかになり始めた2016年である。この年初に黒田が繰り出した唐突ともいえるマイナス金利政策が裏目に出た同年半ば以降、黒田日銀のアピール度はめっきり落ちた。 しかし、ここからが肝心の点である。頼みだった日銀に「全弾撃ち尽くし」の感が出たにもかかわらず、株式市況の強気は崩れなかったのである。安倍の辞意表明直前日の8月27日の日経平均株価は2万3208円と政権スタート時の2倍を超えている。アベノミクスは異次元緩和から乳離れできていたことになる。 なぜそれができたのか。私は、人々が異次元緩和という派手な演出に眼を奪われている隙に、税収の軸足を企業から家計へと移動させていたことにあると思っている。 安倍政権発足前の2012年度には約40%だった日本の法人税率は、2016年度までに大きく引き下げられ、今や30%の大台をも割り込んで現在に至っている。もっとも、これは世界の潮流でもあった。 世界がグローバリゼーションの波に押されるようになった2000年代以降、西側主要国の法人税率は足並みをそろえて低下し、法人税率20%台が自由主義経済圏の世界標準になった感すらある。 安倍政権による法人税率引き下げは、このような「底辺への競争」とも言われる世界的な法人税引き下げ競争にわがニッポンを遅ればせながらも参戦させるものだったのだ。 しかし、法人税引き下げ競争に参戦するには代替財源が必要である。安倍にとってのそれが消費税引き上げだった。安倍は、2014年と2019年の2度にわたって消費税を引き上げ、政権発足前に5%だった消費税率を2倍の10%にまで持ってきている。 安倍政権がそれまでの自民党政権と違うのは、財政再建のためなどという後ろ向きの言い訳に頼らず、「日本を、取り戻す」というスローガンが作り出す高揚感と黒田の異次元緩和が作り出した景気回復感を前面に押し出すことによって、普段なら政権の命取りになりかねない消費税引き上げを、大した抵抗もなく成功させたところにある。 だが、ここで大きな図式から全体を眺めてみよう。法人税とは、要するに売り上げから財サービスの仕入れと人件費を控除した残差である「利益」を対象とする税金である。 これに対し、消費税とは、売り上げから財サービスの仕入れだけを控除した残差である「付加価値」を対象とする税金である。 すなわち、消費税を増税し法人税を減税するという安倍の政策は、企業の賃金支払いへの課税を重くする一方で、企業利益の最終的な帰属先である株主への課税を軽減することを意味するわけだ。安倍政権における税制改革の正体は、労働課税強化を財源にした資本課税軽減なのである。 そこに気づけば、アベノミクスが株式市場とりわけ海外投資家に大好評だった理由もわかってくる。安倍政治あるいはアベノミクスの本質は、低所得層や中間層の犠牲において富裕層を優遇する政策であるばかりでなく、日本国民に負担を押し付けて海外投資家に媚を売るという、時代劇に登場する「悪代官」さながらの裏の顔を持つ政策でもあったのだ。 もっとも、私は、こうした安倍政治の裏の顔を、単純な正義感から批判しているわけではない。増税すれば簡単に国境を越えて出て行ってしまう資本を優遇し、国境を越えるほどの余裕がない人々に国家を支える負担を求めるという政策セットは、グローバリズムが作り出した企業優遇競争に直面した国家たちにおける一種の標準セオリーにほかならなかったからだ。 もし当時の日本が全世界的な資本優遇競争に参加を拒否し続けたとすれば、バブル崩壊後のデフレの底がさらに深くなった可能性だって否定できなかったろう。日本経済を空洞化から救うという文脈では、安倍政治の悪代官性もただの庶民いじめではなかった面もあるわけだ。 だが、それは菅が直面するだろうジレンマを予期させるものでもある。安倍が「一強」とも言える状況を作りえたのは、前の民主党政権や白川方明総裁の下での日銀をデフレの元凶に仕立てる劇場型ともいえる政治手法にあった。 しかし、その手法は、攻撃しやすい「敵」がいなくなれば通用しなくなる。たたき上げ苦労人としての「信頼できそうな人柄」が売りの菅には、劇場型演出によって消費税再引き上げや法人税再引き下げを押し通すだけの腕力はなさそうに思える。 では菅は何をすればよいか。 短期的には、新型ウイルス対策について筋の通った決断をすることである。本年3月から4月にかけての感染第1波を抑え込まないままで経済再開に踏み込んだアメリカの混乱はさておき、日本や欧州主要国ではウイルスの新規感染状況はまさに感染第2波の状況になった。ところが、この第2波におけるウイルスによる死亡状況を見ると、感染者数増とは裏腹に、ほとんどその深刻化を観察できない。 こうした状況で、いつまで「感染即隔離」というウイルス対策を取り続けるのか、そこに政治としての答を求められる日は眼の前に来ているように思う。すなわち「指定感染症」の解除といった明確な方針の表明である。 今回の感染症の性質の変化に人々が気づき始めた今、ただ感染拡大防止をと叫んでいるばかりでは、あの「オオカミ少年」の物語のように、政治も専門家たちも人々の信頼を失うだろう。9月連休における活発な旅行や人出を見ても、その可能性は高まっているのではないだろうか。 だが、より本質的かつ長期的視点から菅に必要なのは、財政をどうするかの議論を始めることである。今回のウイルス禍に対して行われた財政出動は、全国民への一律10万円給付を含め、従来の景気対策的な文脈からのものではない。 景気対策としての財政出動であれば、その見返りは将来の景気回復から得られるはずである。しかし、そうした将来への「投資」という側面を持たない被害者救済的な財政出動の落とし前をつけるためには、従来の課税理論を超えた税体系全体の抜本的見直しが必要なはずである。答えはあるのだろうか。 私は、答えはあると思っている。それは、法人税や個人所得税のような価値分配に対する課税を廃止あるいは大幅に縮小する一方、今の消費税つまり付加価値税の仕組みを拡張し発展させて「拡張付加価値税」ともいうべき新税を創設し、それを軸に税体系の全体を再設計することだ。 拡張付加価値税という考え方そのものについては拙著『ポストコロナの資本主義』(日本経済新聞出版、2020年8月)を参照してほしいが、狙いはファイナンス取引を取り込むことと、勤労者世帯の生計費の控除を可能にすることである。 むろんのこと、危機に備える方法は拡張付加価値税に限られるわけではない。ただ、今回を教訓とするのなら、さまざまな巨大リスクに耐えられる税制の新レジームを設計することは、次への備えの政治的コアであるはずだ。 そうした税制の再デザインにより、フラットで全体整合性のある税体系を準備しなければ、次の危機に備える財政の機動性を確保することなどできるはずがない。それを避けてデジタル庁新設などという行政統廃合でお茶を濁していれば、菅内閣は単なる中継ぎ政権で終わるほかはあるまい。 安倍政治の継承という看板を掲げ続けるだけでは、菅は「悪代官」にすらなれないだろう。 岩村 充 :早稲田大学大学院経営管理研究科教授 【出典】東洋経済オンライン 9/30(水) 5:11配信
|
 |
|||
|---|---|---|---|
 来週には辞任するというのに、この男は最後まで国民を舐めきった態度を貫くらしい。 昨日11日、憲法にも国際法にも反する「敵基地攻撃能力」保有の検討を事実上、進める方針を打ち出す「談話」を発表した安倍首相だが、その夜、公邸で、安倍首相のスピーチライターである谷口智彦内閣官房参与や鈴木浩外務審議官と約2時間、会食をおこなったと朝日新聞が報道。谷口参与によると、なんと〈コース料理を完食し、ワインも口にしていた〉というのだ。 そもそも、本サイトでも昨日取り上げたように、「政治判断を誤る」恐れがあると言って辞意を表明した安倍首相が、総理大臣として責任もとれないのに「談話」を発表して国の方向性を左右する重大な方針をこの期に及んで打ち出すこと自体、とんでもない話だ。 だが、それだけにとどまらず、夜の会食をおこない、コース料理を平らげてワインまで口にしていたとは……。 言っておくが、わずか2週間ほど前に持病の潰瘍性大腸炎の悪化を理由に政権を放り出したばかりなのだから、しばらくは職務以外は静養に務めるのは当然だ。ましてや安倍首相はまだ首相在任中だ。酒席を控えるのは当たり前だろう。 その上、本日午前には、安倍首相はかかりつけの慶應義塾大学病院を受診。昨日、本サイトでも指摘したように、安倍首相は辞意表明会見前は2週連続で同院を受診していたが、その後は一度も受診せず、きょうは約3週間ぶりの受診だ。 これらの報道を受け、ネット上では〈ん?通院の前日の夜にフルコース食ってワイン飲んだの?〉〈きのう宴会に出席して、フルコース完食&飲酒してたじゃねえかコイツ〉〈私なら、私ならばだけど、病院行く前夜に、お酒は飲まないし、コース料理食べないわな〉といった当然のツッコミが寄せられている。 いや、フルコース会食だけではない。今週発売の「週刊文春」(文藝春秋)では、首相周辺の関係者がこんなことを漏らしているのだ。 「内閣支持率も政権末期としては異例の六割超えで、本人も上機嫌。茂木敏充外相など、会う人会う人からゴルフの約束を持ちかけられているそうです。菅陣営の事務総長、山口泰明衆院議員も『総理とゴルフの約束をしたよ』と言っていました」 「病気と治療を抱え、体力が万全でない」と言って総理大臣を辞めると宣言した人物が、「通院前夜にコース料理完食&アルコール摂取」に「ゴルフの約束」……。ここまでくると安倍首相は「持病が悪化」なんてしていなかった、病気は政権放り出しの言い訳にすぎなかったとしか考えられない。 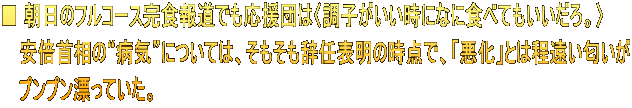 本サイトで何度も指摘しているように、辞任表明会見では、6月に潰瘍性大腸炎再発の兆候がわかり、7月中旬に体調に異変を感じたと説明していたが、首相動静を見ると、体調異変の以降も連日、ステーキやフランス料理などの会食ざんまいの日々を送っていた。 また、健康不安を理由に辞任を宣言しながら、会見では入院や静養はせず、「(後任が決まるまでの間)私の体調のほうは絶対に大丈夫だと思っております」と執務を続けることを宣言。 さらに、今後について聞かれると、「次なる政権に対してもですね、影響力……」と言いかけて、慌てて「一議員として協力していく」と言いなおす始末だった。 これらをみるだけでも、安倍首相の本当の辞任理由が「病気の悪化」ではなく、コロナ危機や支持率低下、見通しの立たない政治状況に嫌気がさして政権を投げ出したことは明らかだった。 ところが、安倍応援団や側近が重病説を煽り、仮病疑惑を追及しようとする言論を「病気の人をそんなに貶めたいか」と攻撃したことで、メディアも追従。安倍首相はすっかり「病気のせいで二度も志半ばで倒れた悲劇の宰相」ということになってしまった。 昨晩のフルコース会食も同様だ。会食の詳細を伝えた朝日の報道、それを受けて「本当に病気なのか?」「仮病なのでは?」という疑念の声が出ると、またも以下のような攻撃が加えられたのだ。 〈調子がいい時になに食べてもいいだろ。〉 〈リプ欄、少し調子が良い時にマトモな飯を食うのすら否定する人ばっかりで悲しくなるな。そりゃあブラック企業も過労死も自殺も無くならないわけだよ。〉 〈元気になって良かったではないか。総理が快復されるのは気に入らないようだな?朝日新聞は印象操作して何が言いたいんだ?腐った新聞社だ〉 〈病気療養中なので安倍総理のコースは、他の人とメニューが違った可能性もあるのに完食したというだけで反安倍の人達は嘘つきだ、仮病だと憶測で言いたい放題です〉 こうした攻撃には、そもそもの大前提がすっかり抜けている。安倍首相は一般人ではなく、本人も明言してきたように「国家の舵取りを司る重責」を引き受ける総理大臣という重大な立場に立つ者だ。それを、安倍首相は新型コロナという「国難」の最中に「病気」を理由に辞任すると自ら決めた。 ならば、首相在任中は少なくとも病気に差し支えるアルコールを控えるなど養生に務めるのが、国民に対して最低限の礼儀というものだろう。 なのに、国民に対してとるべき姿勢も見せず、側近が「コース料理を完食し、ワインも口にした」などと漏らし、国民に「本当に病気なのか?」「仮病なのでは?」と思わせるような行動を平気でとっているのである。当然、批判されるべきは政権を途中で投げ出した安倍首相の無責任ぶりのほうなのだ。 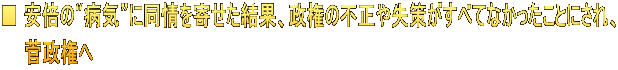 ところが、ネット上ではこの期に及んでもなお、安倍首相が途中で責任を放り出した総理大臣であることをネグり、「病人を差別するのか」などというデタラメな理屈で批判を封じ込める動きが起きている。 そして、本来は朝日を後追いして病状について徹底して追及・検証すべきメディアもそうした恫喝を恐れて口をつぐんでしまっている。 そして、深刻なのはこうしたネットやメディアの動きがそのまま国民の意識に反映されていることだ。多くの国民は安倍首相が病気の悪化で辞任したことを信じて疑わず、すっかり同情を寄せてしまった。 その結果、内閣支持率は爆上がり、共同通信の世論調査(8月29・30日実施)では56.9%にまでのぼった。さらに「安倍首相の傀儡」である菅義偉官房長官も総裁選で「安倍政権の継承」を打ち出し、支持率を上げた。 新型コロナ対応でさんざん批判を浴び、地に落ちていた支持率が「病気」ひとつで逆転し、いまだに責任追及がおこなわれるべき問題が山積した状態にあるというのに、それを「継承」すると打ち出した菅官房長官が支持される──。つまり、「病気」という錦の御旗によって、「安倍政治」は完全に息を吹き返したのだ。 そして、こうして同情により息を吹き返したことによって、安倍政権の「負の遺産」も、まったく責任がとられないまま菅官房長官によって継承されようとしている。 実際、本日おこなわれた日本記者クラブ主催の総裁選討論会では、公文書改ざんを命じられ追い込まれ自殺した近畿財務局の職員・赤木俊夫さんの妻が再調査を求めている問題について、菅官房長官は「財務省で調査をし、検察でも捜査した。結果は出ている」「再発防止策をこれからしっかりとつくっていく」と“終わったこと”として片付け、記者から“財務省の調査は身内によるものでしかない。 安倍昭恵氏や政治家の名前が文書から消された点など改ざんの経緯は明らかになっていない”と指摘されても、「いま私、申し上げたとおりです」と取り付く島もなかった。 政治責任の追及が不完全なままなのは、森友問題だけではなく、加計学園問題も「桜を見る会」問題も同じだ。 本当ならば、その全容が解明され、安倍首相が数々引き起こしてきた「政治の私物化」について安倍首相は責任をとらなければならないが、そうした追及・検証が「病気」によってなぜか幕が下ろされてしまった。 そして、それらが何の問題もなかったことのように「継承」されようとしている──。ようするに、「病気」がすべてに蓋をしてしまったのだ。 いや、それどころか、安倍応援団はすでに「第三次安倍政権」待望論を唱え始めている。第一次政権から第二次政権へと復活した際も、安倍首相は“病気で断念せざるを得なかった無念の思いを再びかなえる”などといったふうに政権投げ出しを美化し、利用したが、それが再び繰り返される可能性は十分ある。というか、国民世論がそれを後押ししているような状態だ。 「病気」を理由に批判が封じ込められてしまう状況があるかぎり、問題の全容解明も責任を明確にすることも、安倍政治にケリをつけることもできない。菅政権による悪政の継承、そして「安倍第三次政権」を阻止するためにも、病状も含め、安倍首相への追及を終わらせるわけにはいかないだろう。 (編集部) 【出典】LITERA 2020.09.12 10:18
|
 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
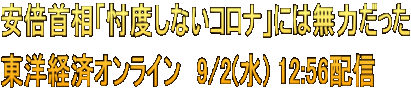 7年8カ月に及ぶ在任期間を「攻め」の姿勢で駆け抜けてきた安倍晋三首相。だが、こと未知のウイルスには通用しなかった。数々の難局に対して批判に正面から答えず、国会での答弁拒否や文書改ざんで乗り切ってきた政権だが、ウイルスには無力だったといえる。健康の問題を理由に退陣することについては気の毒に思う。だが、政策の評価に同情を差し挟めば、次につながる教訓を見失う。 【データで見る】新型コロナウイルス 国内の感染状況 安倍政権は、同盟国のための武力行使を可能にする集団的自衛権という憲法の根幹を問う安全保障関連法の成立を強行した。そのほかにも、秘密を漏らした公務員を罰する特定秘密保護法、組織犯罪を準備したとみなされれば罪に問われるいわゆる共謀罪など、平和や人権に大きな変化をもたらしかねない法律を次々と成立させた。 野党や国民から批判の声が上がっても、正面から答えない詭弁を弄して、数の力で政権を維持してきた。「戦後レジームからの脱却」を掲げた、いわば安倍流の「攻め」の姿勢だ。 強硬な「攻め」を担保する「地ならし」にも余念がなかった。元防衛相の石破茂氏、元総務相の野田聖子氏、東京都知事の小池百合子氏といった、自分の地位を脅かしそうな政治家を遠ざけ、苦言を呈する議員には選挙区に刺客を送り込んで落選させた。 ターゲットは官僚にも向けられる。中央省庁の幹部人事を一元管理する「内閣人事局」を発足させ、人事を官僚主導から政治主導に変えた。官僚が官邸に抵抗しにくいシステムを築き上げたのだ。首相の周囲は、経済産業省など経済活動を推進させる立場の役人が補佐官として張り付き、経済優先の路線をひた走る。 仕上げはメディアへの圧力だ。気に入らない報道には抗議するなどのほか、批判的なテレビ局には出演しない。首相の会見でも事前に質問を通告するよう求めるなど、制約が課せられた。やがてメディア側にも、官邸の意向を斟酌(しんしゃく)しなければ仕事がやりにくいという空気が育まれていった。これで忖度政治の完成だ。次第に批判は封じ込められ、政治は民意とはかけ離れたものになっていく。 首相の在任中、守勢に回ったのが「もりかけ問題」や「桜を見る会」だ。野党の追及も決定打を欠いた点も否めないが、首相は正面から追及に答えようとせず、逆に公文書の改ざんや廃棄などで難局を生きながらえてきた。庶民感覚を見失った宰相には、9億5600万円の国有地を1億3400万円で払い下げることの不自然さと、それに不公平感を覚える庶民感覚を理解できなかったのかもしれない。そのことによって近畿財務局の職員が自殺したことを、首相は自分の責任だと考えたのだろうか。 その宰相を襲ったのが、得体の知れない新型コロナウイルスだった。ウイルスばかりは忖度はしてくれないし、詭弁も通用しない。おまけに政治家や官僚とは違う、科学的な根拠を重視する公衆衛生や感染症の専門家の力を借りなければならない。詭弁とは対極にあるこれらの専門家には、もちろん永田町の論理が通じるわけもなかった。首相在任中、初めて経験する事態に安倍首相も戸惑ったに違いない。 コロナ対策で、まず安倍首相が手掛けたのは、2月27日に全国の小中高校に対して行った「休校要請」だった。首相が信を置く側近の今井尚哉首相補佐官の進言を受け入れて決断したと言われている。桜を見る会などで支持率を落とした首相にとって、起死回生の一策だったのかもしれない。だが、学校が休校になれば働く親たちが窮地に追い込まれることは容易に想像できる。とくに当時は子どもが感染しても重症化に至る率は低いことがすでにわかっていた。科学的根拠に基づかなかった一斉休校は、庶民の暮らしへの配慮を欠いていた。 防戦を強いられた首相の次の一手も、批判のターゲットとなる。 アベノマスクだ。 全国的なマスク不足を解消するためのアベノマスクは、今井補佐官とは別の補佐官の「全国民に布マスクを配れば不安はパッと消えますよ」との進言を受け入れたと言われている。当初は466億円をつぎ込むとされたが、PCR検査の殺到で機能不全に陥った保健所や地方衛生研究所の態勢整備が叫ばれていた時期でもある。「ほかにやることがあるのでは」「エイプリルフールか」などと非難の嵐に見舞われた。 結局、各戸に配られる頃にはマスク不足も解消され、菅義偉官房長官が会見で「布マスクの配布により需要が抑制された結果、品薄状況が改善された」などと、根拠の脆弱な言葉が失笑を招いた。 さらに追い打ちをかけたのが、緊急事態宣言の期間中だった4月12日に首相がインスタグラムにアップした動画だ。愛犬を抱いたりティーカップを手にくつろいだりして、「皆さんのこうした(自粛)行動によって、多くの命が確実に救われています」などと呼びかけるメッセージが添えられた。 当時といえば、自粛生活を強いられる多くの国民は不安に陥り、戸惑いが広がっていた。店の経営資金に窮して途方に暮れる自営業者や、多くの人が仕事を追われて失職し、明日の生活さえままならない絶望感に打ちひしがれていた。そんななかで、一見すると優雅に見える動画は、逆に反感を買うことになる。これも庶民感情を見誤った粗忽(そこつ)の極みだ。 一方、コロナ感染の防御対策も後手に回った。3月下旬に感染者が急増して医療現場が悲鳴を上げていた時期、専門家からも緊急事態宣言の必要性が訴えかけられたが、経済を懸念した官邸が宣言したのは4月7日だった。しかも自粛要請を求める業種などで東京都と折り合いがつかずにずれ込む不手際もあった。 首相は国民の前に出る機会が極端に減っていく。緊急事態宣言は5月25日、7週間ぶりに全面解除されたが、この日の首相会見以降、国会が閉会する6月18日まで、首相は一度も記者会見を開いていない。最後の会見は、広島の平和祈念式典に出席した8月6日で、わずか15分間だった。国を挙げてウイルスと闘っているとき、首相は明らかに腰が引けていた。  首相会見でこんな場面があった。 緊急事態宣言の延長を受けて開かれた記者会見の5月4日だ。ビデオジャーナリストの神保哲生氏の「検査を増やせと指示しても増えないのは、本気で増やそうとしなかったからなのか、増やそうとしたが増えなかったのか」との質問に、首相は、こう答えた。 「本気でやる気がなかったというわけではまったくありません。いわば人的な目詰まりもあった」 自分は頑張っているが、PCRを担う保健所や地方衛生研究所の目詰まりに責任を負わせるような口ぶりだ。 だが、実はこの保健所や地方衛生研究所の態勢整備は、自民党政権が棚上げしてきた感染症対策上、重要な“教訓”だった。 2009年の新型インフルの流行時の反省を踏まえて、今後の感染症対策のあるべき姿を検討した「新型インフルエンザ対策総括会議」の報告書では、「保健所や地方衛生研究所を含めた感染症対策に関わる危機管理を専門に担う組織や人員体制の大幅な強化、人材の育成を進める」と提言されている。 この総括会議の報告書が完成したのは2010年7月で、民主党政権下での提言だった。その後を継いだのは2012年末に政権交代を果たした自民党の安倍政権だった。にもかかわらず、保健所の拡充をせず、地方衛生研究所の法的裏付けも放置してきたのは安倍政権なのだ。 報告書では、このほかにも、アメリカCDC(疾病対策センター)などを参考にして、よりよい組織や人員体制を構築すべきである」などの提言がなされているが、予算措置を伴うものについては放置されてきたのが実情だ。 かつて「悪夢のような民主党政権」と放言した安倍首相。確かに国政を安定させるなど功績は少なくない。だが、こと感染症対策においては、同じ言葉を返されても抗弁できないはずだ。 コロナ禍が深刻化する3月には、「私が決断した」などと、政治主導をアピールする言葉を連発し、6月の会見では、「日本モデルの力を示した」と胸を張った首相だが、実の伴わない首相の言葉に信憑性を見いだせた国民がどれほどいただろうか。 他国ではそれぞれのリーダーたちが、よいも悪いも、その“言葉”によって影響力を行使していた。それと比べて、安倍首相の存在感は薄れるばかり。忖度とは無縁の未知のウイルスに安倍流は通用しなかった。 辰濃 哲郎 :ノンフィクション作家 【出典】東洋経済オンライン 9/2(水) 12:56配信
|
 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
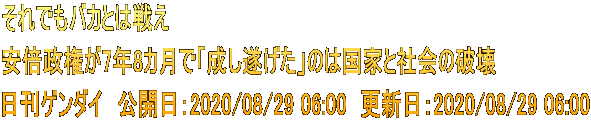 安倍晋三の首相連続在職日数が24日で2799日となり憲政史上最長となった。 安倍は「政治においては、何日間在職したかでなく、何を成し遂げたかが問われるんだろうと思うが、この7年8カ月、国民の皆さまにお約束した政策を実行するため、結果を出すために一日一日、その積み重ねの上にきょうの日を迎えることができたんだろうと考えている」とコメント。 え? どこのパラレルワールドの住人か知らないが、成し遂げたのは社会の破壊くらいだし、国民との約束を守らなかったことが現在問題になっているのにね。 自民党は2017年に党則をねじ曲げ総裁任期を「連続3期9年」に延長したが、二階俊博も甘利明も麻生太郎も安倍4選に言及。永久に安倍を担ぐ算段だったのかもしれない。しかし、現実世界ではそれは無理。 8月17日、東京・信濃町の慶応大病院を安倍は訪れ、約7時間半滞在。同24日にも再び病院を訪問した。安倍周辺は「前回の続き」と説明したが、持病の潰瘍性大腸炎が悪化したという説や、検察の捜査(公職選挙法違反)から逃れるための入院の準備といった説も流れた。 こうした中、SNSでは「さっさと死ね」といった類いの意見が散見されたが、乱暴なことは言ってはいけない。病気になったのは安倍の責任ではない。それに今、死んだら逃げ得だ。一連の「安倍晋三事件」の追及がうやむやになる可能性もある。 安倍が7年8カ月で日本に与えたダメージは凄まじい。北方領土をロシアに献上し、アメリカからはガラクタの武器を買い、拉致問題を放置。国のかたちを変えてしまう移民政策を嘘とデマで押し通し、森友事件における財務省の公文書改ざんをはじめ、防衛省の日報隠蔽、厚生労働省のデータ捏造などで国家の信用を地に落とした。 安倍は、水道事業の民営化や放送局の外資規制の撤廃をもくろみ、「桜を見る会」には悪徳マルチ商法の会長や反社会勢力のメンバー、半グレ組織のトップらを招いていた。 この悪党を支えてきたのがカルトや政商、「保守」を自称するいかがわしい言論人だった。 今、安倍がやるべきなのは無理をせずにしっかりと体調を整え、わが国で何が発生したのか、この先の検証に協力することだ。 【出典】日刊ゲンダイ 公開日:2020/08/29 06:00 更新日:2020/08/29 06:00
|
| 【出典】日刊ゲンダイ 公開日:2020/08/29 06:00 更新日:2020/08/29 06:00 |
 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
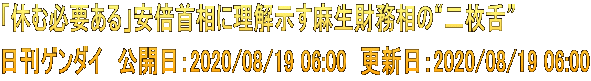 「147日間休まず働いたら、普通だったら体調としては、おかしくなるんじゃないの」「休む必要があるということは申し上げた。ちゃんと自分で健康管理するのも、仕事の一つだ」 安倍首相が17日に東京都内の病院で「日帰り検診」を受けたことに触れ、こう語っていた麻生財務相。 国民に自粛生活を呼び掛けつつ、自宅のソファで愛犬と優雅に過ごす姿をネットに投稿していた安倍首相が、この約5カ月の間、ほぼぶっ続けで働き続けていたとは到底思えないが、それはさておき、麻生財務相は安倍首相が休めなかった理由として「新型コロナウイルスへの危機対応」を挙げたかったらしい。 「突然の出来事で忙しかったのだから、休むのは当然ではないか」というわけで、もっともらしく聞こえるものの、麻生財務相はかつてブログでこう主張していた。 東日本大震災、福島原発事故という未曽有の危機への政府対応が迫られた2011年の6月23日付だ。 <この通常国会は、昨日の衆議院本会議をもって、70日間の延長となった。ここで、はっきりさせておかなければならないことは、我々自由民主党は、延長そのものに反対したことはないということだ。我々は、被災地で災害からの復旧・復興が端緒に就いたついたばかりの段階で、国会議員が夏休みを取れるはずがないと、6月22日で国会を閉じようとされていた菅首相の対応に対して、厳しく物申してきた> 野党時代は、災害からの復旧、復興のためには<国会議員が夏休みを取れるはずがない>と言っていたにもかかわらず、自分たちが政権の座に就くと一変。新型コロナへの対応を求める国民の声に耳を傾けず、<休む必要がある>などと真逆のことを言っているからムチャクチャだろう。 <今の状況を考えたとき、被災地の復興や外交の立て直しなど、政府がやらねばならないことはいくらでもある。そういったことを進めるに当たって、何が障害になっているかといえば、菅内閣総理大臣の存在そのものがその一つになっていると、確信している。菅直人総理大臣が復興の最大の阻害要因、我々はそう言い続けてきたし、今もそう思っている。したがって、菅首相に辞めていただくことが、日本の為、復興の為になると、申し上げてきた> 麻生財務相は2011年6月のブログでこうも書いていたが、野党側が求めた国会延長を蹴飛ばし、さらに臨時国会の召集要求も無視しているのは何処の誰なのか。 麻生財務相の言葉を借りて言えば、新型コロナの感染防止と景気回復のための<障害><最大の阻害要因>となっているのは間違いなく安倍首相の存在だ。 麻生財務相が安倍首相に言うべきは<休む必要がある>ではなく、<辞めていただくことが、日本の為、復興の為になる>だ。 【出典】日刊ゲンダイ 公開日:2020/08/19 06:00 更新日:2020/08/19 06:00
|
| 【出典】日刊ゲンダイ 公開日:2020/08/19 06:00 更新日:2020/08/19 06:00 |
 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
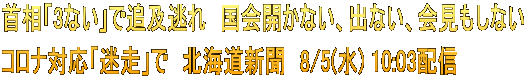 臨時国会を開かない、閉会中審査に出ない、記者会見しない―。新型コロナウイルスの感染再拡大が続く中、安倍晋三首相の発信力低下が際立っている。三つの「ない」には、野党や記者からコロナ対応などに関する追及を回避する思惑が透ける。 「私もこうした形で節目節目に話をしているが、菅義偉官房長官も西村康稔経済再生担当相も毎日会見を行い、説明している」。首相は4日夕、官邸で記者団から臨時国会や記者会見を開くよう求められ、こう答えた。「それでも国民は不安だ」と指摘されても同様の説明を繰り返し、「逃げないでください」という声も飛んだが、答えずに官邸を後にした。 政府・与党は早期の臨時国会召集に否定的だ。菅氏は4日の記者会見で「今はコロナ対策に全力を尽くすべきだ」と主張。観光支援事業「Go To トラベル」を巡る迷走や新型コロナウイルス特措法改正などが国会審議で取り上げられ、政権への打撃になることを避けたいのが本音だ。 首相には国会出席のために時間を取られることへの不満もある。昨年11月の参院予算委員会では「世界で私はおそらく最も、圧倒的に多くの時間を国会で質疑に応じている」と持論を展開している。 与党は、首相が閉会中審査に出席して説明責任を果たすべきだとの野党の要求も拒み続けている。閉会中審査は毎週開かれているが、これまで首相の出席はゼロ。自民党幹部は「首相の出席は(閣僚との)屋上屋になる」としているが、首相が矢面に立つのを防ぎたい意図は明らかだ。 約1カ月半、記者会見しない理由も同様だ。首相は会見を批判的に報道されることを気にしているといい、コロナ感染拡大後の会見の多くを外交日程などを理由に途中で打ち切ってきた。河井克行前法相、案里参院議員夫妻の事件や森友学園問題など、コロナとは無関係の問題でも追及されるのを避けたいようだ。 西村氏は4日で会見の実施日数が100日を数えたが、お盆の帰省を巡り菅氏と見解が食い違うなどの弊害も出ている。そもそも、一国の首相が発信するのとは重みが異なる。 立憲民主党の枝野幸男代表は4日の会見で政府の対応を「朝令暮改、閣僚ごとに言うことが食い違い、無政府状態と言っていい。一刻も早く退陣し、別の首相の下で対策に当たっていただくのが国家に対する責任だ」と酷評。自民党幹部ですら「政治家という商売は逃げていたら成り立たない」と苦言を呈した。(石井努) 【出典】北海道新聞 8/5(水) 10:03配信
|
| 【出典】LITERA 2020.06.16 10:57 |
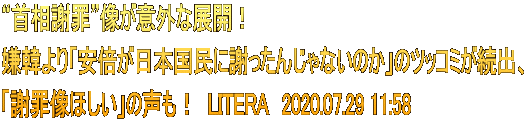 韓国の民間の植物園で、慰安婦問題を象徴すると思しき少女像に安倍首相らしき男性がひざまずいて謝罪する像が設置されたというニュースに、また安倍政権とネトウヨが大騒ぎしている。 とくに28日午前の会見で菅義偉官房長官がこの件について「国際儀礼上、許されない。報道が事実なら日韓関係に決定的な影響を与える」などと不快感を表明したことが報じられると、「首相謝罪」がトレンドワードにまでなった。 しかし、問題はその後。いつものように、ネトウヨの韓国ヘイトがさらに拡大し、メディアが嫌韓一色になると思いきや、まったく意外な現象が起きている。嫌韓どころか、「安倍首相がコロナ対策の不手際を国民に謝った」と勘違いした人が続出しているのだ。 実際、ツイッターを見ると、こんな声であふれている。 〈首相謝罪、てっきり今までのコロナ対策の怠慢や無策を国民に詫びるとかだと思ったら違った。〉 〈トレンドに首相謝罪とあったので、めずらしくコロナ対応等で、 国民に謝罪会見でもしたのかと思ったら・・・〉 〈#首相謝罪 てっきり、税金を無駄な使って、ごめんなさい!と国民に謝罪した。と言うことだと思ったのに。 そんなことありえないか?(笑い)意固地だもんね。#アベノマスク に命かけているもんね。〉 〈コロナ対応や水害の被災者支援についての対応遅れについてかと思ったらちゃうのね〉 〈首相謝罪っていうから、コロナ禍で世界中が大変な時にさっさと国会閉めてろくな舵取りもしないで沈黙してごめんなさいってようやく謝って仕事する気になったのかと思ったらあれ?全然違う話?〉 〈トレンドの首相謝罪をみてしまった。 そっちの事でしたのね。 てっきりこのコロナのダメダメな世の中に謝罪かと思ってしまいました。〉 〈アベノミクスが全く嘘っぱちのゴミ施策でしたので国民へ謝罪するとかじゃ無いのね... #首相謝罪〉 〈トレンドに「首相謝罪」とあったので、国民に今までの不手際、私物化をようやく認めて謝罪したのかと思ったら、違う件でした。〉 GoToキャンペーン強行やアベノマスクの追加8000万枚配布という愚策が大炎上していたことから、その件につい謝罪したのかと勘違いした人も多かった。 〈首相謝罪って、私も国民にかと思った。 「マスク、めっちゃ儲かるので2回目しようとしてました。すみません!」かなぁって。〉 〈トレンドに #首相謝罪 ってあったけど、これを謝罪したわけじゃなかったのか。すみません、誤発注でした!とか。 布マスク、今後さらに8千万枚を配布 不要論でも発注済〉 〈首相謝罪?って、私は首相が布マスク配布やGOTOトラベルで無策で迷惑かけているのでてっきり国民に謝罪する件なんだとおもったんだが。〉 〈首相謝罪とかいうから、ついに国民に向けて「アホな政策で税金を無駄遣いしてしまい大変申し訳ございませんでした。」を言う気になったかと思ったら全然違った〉 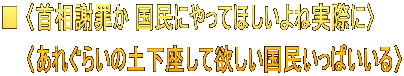 しかも、驚いたのは、「首相謝罪」というのが、韓国に設置された安倍首相の謝罪像の件だったとわかったあとも、像や韓国には全く関心を示さず、むしろ、安倍首相が国民に謝罪したわけじゃなかったことへの失望を表明する声が相次いだことだ。 〈首相謝罪???とか思いながら開くと、あぁそういう事ねとw こっちはこっちで災害とかコロナで大変なんだから、あんなの放っとけばいいんじゃないですかね。〉 〈首相謝罪って国民に対してかと期待してしまったけど覗いたらつまらなくて草〉 〈首相謝罪っていうから国民に対してなんかしたんかと思ったけど像についてか、くだらん。〉 〈#首相謝罪 がトレンドに入ってるのを見て、ずさんなコロナ対策と感染者が増えてる中強行したGoToキャンペーンについて安倍総理が謝ったのかと思ったんだ。 そしたら韓国の植物園が置いた、慰安婦少女に謝る安倍総理に似た男性の像の事だったんだ。〉 〈首相謝罪ってあの像の事かよ!! こんな像作る余裕あるとか、よっぽど平和で暇な国なんだろうなぁ。 いいなぁ。 日本はコロナで大変ですよw〉 〈俺たち国民に謝罪したのかと思った。 というか思いたかった。 #首相謝罪〉 〈日本のトレンドに「首相謝罪」とあったので,ようやく安倍首相もおのれの愚策に気づき,政策転換を図るために全国民に対して謝罪をするのかと期待したら,全くの「ぬか喜び」だった。〉 〈日本国民に謝罪だとみんな思ったろうなあ。がっかり。〉 さらには、これをきっかけに、安倍首相に対して実際に国民に謝れ、と迫る動きまで出てきている。 〈安倍ちゃん国民に謝れ〉 〈トレンドに「首相謝罪」ってあるけど、コロナ対策もロクにしてないし、まずお前が謝罪しろ。〉 〈慰安婦像にする必要は無いが、税金を無駄使いしやがったことを国民に謝罪しろ。 #首相謝罪〉 〈首相謝罪か 国民にやってほしいよね実際に〉 〈首相謝罪像わろた 慰安婦はともかく、安倍さんは今すぐ日本国民に謝った方がいいと思うよ〉 〈首相謝罪?韓国に謝罪はいらんよ。安倍は日本国民に謝罪してくれよ。〉 〈むしろ日本国内にも多数、あれぐらいの土下座して欲しい国民いっぱいいるけどね。いや、土下座いらんから、1秒も早く政界やメディアから消えてくれ。言動の全てが日本の害悪〉 〈国民に謝罪せえよ 色々あるやろ 広島の議員のことや ありすぎて忘れるわ #首相謝罪〉 〈#首相謝罪 また使えないマスク8000枚配るバカはマジで国民に土下座しろ〉 〈コレはけしからん。 安倍が謝るべきは、今までさんざん欺き搾取してきた日本国民に対してだろ‼️ 日本でも韓国でも阿呆なエセ右翼は、ろくな事しないな。 #首相謝罪〉 〈首相謝罪ワロスwwwww安倍も菅もまずは日本国民に謝れwwwww〉 〈#首相謝罪 日本国民に対して謝罪してくれよん。 特に水害被災地に(支援遅すぎで)〉 〈殊勝なことに首相が国民に謝罪したのかと勘違いしたわw 韓国に謝るかどうかはともかくとして、土下座はこうするんだと理解する機会があってよかったじゃないか、安倍晋三。 #首相謝罪〉 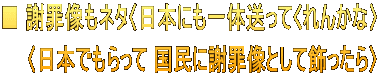 しかも、対象は安倍首相だけではない。菅官房長官が不快感を表明したことにも、賛同どころか、「お前こそ土下座しろ」のツッコミの声があふれた。 〈安倍の謝罪像に菅がキレてるけど、安倍総理が他国からdisられようと、もはや何とも思わないなぁwww むしろ日本国民に対して土下座謝罪して欲しい気分なんだけど。 ずさんなコロナ対策について。〉 〈ガースー、お前も含めて実物の安倍夫妻に対し日本国民〔一部を除く〕も不快感だよ〉 〈首相謝罪はこの半年の日本国民への仕打ちにまずすべきだと思うの。やることやりもしないで不快感とか、何吠えてんの。〉 〈菅氏「首相謝罪」像に不快感 - Yahoo!ニュース そうだよな、まず日本国民に散々税金で好き勝手してごめんなさいって土下座をするのが先だよな。〉 〈首相謝罪…菅が不快感? 日本国民は普段、キミたちに不快感を露わにしていることに気付いていないのかい? キミたちは日本国民に土下座するべき立場なんだよ。それを渋って、いつまでも椅子温めて国民から税金搾取してお友達ごっこやってるから、日本国民に代わって制裁が下されただけのこと。〉 〈ホント不愉快ですね。 そんな像にムキになる前に「国民に対して」言うことないのか? 内面より外面の政府。 そのくせ「もっと安倍総理なら男前だ」位言って笑い飛ばす器量も無く1公園のモニュメントに「安倍総理様がー」って?〉 〈首相謝罪像とか自分のことに関してはめちゃくちゃ敏感なくせに国民の声は聞こうとしないよな。きも〉 さらには、謝罪像そのものをネタにして、こんなツッコミまで飛び出している。 〈首相謝罪像の頭を日本国民の方に向けて設置するべきなのでは〉 〈首相謝罪像って韓国にあると問題やけど 日本でもらって 国民に謝罪像として飾ったら 問題ないジャマイカ〉 〈日本にも一体送ってくれんかな〉 〈「首相謝罪の像」、日本にも何個か設置したいと思いませんか? 例えば福島とか、森友小学校跡地とかに。〉 〈この土下座する安倍像、是非とも日本でも作って国民の像と共にこんな感じで展示したい。 お粗末なコロナ対応で国民を苦しめた責任は重いでしょ。〉 〈その像(安倍が謝る像)は日本が作るものです 安倍晋三は韓国ではなく日本国民に謝るべきです〉 〈慰安婦像にではなく 国民に土下座してほしい この像 日本に寄贈してくれないかなぁ〉 〈首相謝罪像?国民に対しての像を国会議事堂入口に作ったら?〉 〈見ましたよ!本当に大笑い あの像は日本国民に対して使った方がいいだろ?〉 これまでのパターンなら「安倍首相に土下座させる像を置くなんてけしからん」というヒステリックな声がネットを覆い尽くすはずが、「首相謝罪像を日本にほしい」「日本でも設置してくれ」とは。しかも、こうしたツッコミをしているのは、以前から政権を批判してきたリベラルの人たちだけではない。文面やアカウントを見ると、ふだんは韓国に対して差別的な言説を連ねるネトウヨ的な人まで含まれていることがよくわかるのだ。 いったい、これはどういう変化なのか。というのも、ここ数年、日本ではネトウヨや安倍応援団だけでなく、とくに政治に興味のない人や、安倍政権に批判的な人のなかからもライトな嫌韓発言が出てくるなど、韓国ヘイトの空気が支配的になっていた。 そして安倍政権もまた、政権不祥事や悪法の強行採決などに対する批判をごまかすために、この嫌韓を利用してきた。なかでも象徴的なのが昨年の韓国に対する唐突な輸出規制で、これも参院選に合わせて嫌韓を煽り政権浮揚をはかるための差別政策そのものだった。 今回の安倍首相謝罪像問題も、安倍官邸は明らかにいつものように失政をごまかすために利用しようと、扇動を仕掛けていた。 韓国政府がまだ何のコメントも出していない時点で、菅官房長官がわざわざ会見で触れたという事実からもそのことはうかがえる(しかも、韓国政府はその後「どの国であっても外国の指導者クラスに対してそうした国際礼譲を考慮する必要がある」として像を批判している)。 普段は重要な問題について「コメントする立場にない」などと無視する菅官房長官が、それこそ本来「コメントする立場にない」はずの他国の民間人の表現活動について、「許されない」などとコメントするなんて、普通は考えられない。それこそ「韓国はひどい」「安倍さん負けるな」といった声を引き出すために、わざわざニュースを大きくしたのである。 ところが、上述のように、まったく嫌韓は盛り上がらず、逆に「安倍首相は国民に謝れ」「謝罪像を寄贈してもらって日本に設置しろ」という声が噴出する羽目になってしまったのだ。 これはもちろん、国民の意識が大きく変わったからだ。これまでは嫌韓に踊らされていたが、コロナ対策をみて、韓国よりはるかに日本の安倍政権がひどいということに気がついてしまったのである。 実際、ワイドショーなどでも最近は、嫌韓特集がまったく数字が取れなくなっているという。各番組はそれでも、北朝鮮との関係悪化、軍艦島の世界遺産登録に韓国が取り消し要求、G7参加、ビザ問題、慰安婦支援団体の不正などを取り上げていたが、視聴率が振るわず、結局、散発的に終わっている。 そういう意味では、これまで政権に怯え、忖度してきたマスコミもそろそろ意識を変えるべきではないのか。 〈国民に対して謝罪したのかと思ったら違ったわ。 国民に首相謝罪して、そして辞めて。仕事しない首相など要らない〉 これが大多数の国民の声なのだ。時代遅れの嫌韓をやってる場合ではないのである。 (編集部) 【出典】LITERA 2020.07.29 11:58
|
|---|
| 【出典】LITERA 2020.06.16 10:57 |
 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
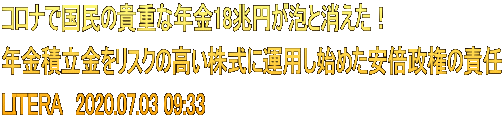 一体、この失敗の責任を安倍首相はどう負うのか。本日、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2020年1~3月期の公的年金積立金の運用実績を発表したが、なんと、過去最大の損失額となった2018年10~12月期の14兆8039億円をはるかに上回る、17兆7072億円の赤字となったのだ。 さらに、2019年度の運用実績のほうも8兆2831億円の赤字となり、リーマン・ショックがあった2008年に9兆3481億円の損失を叩き出して以来、過去2番目の損失額を記録。こちらも2020年1~3月期の赤字が大きく響いた格好だ。 無論、今回ここまでの赤字を叩き出したのは新型コロナの影響によって世界的に株価が値下がりしたことが原因だ。実際、すでに4月の段階から1~3月期の運用が17兆円前後になると民間エコノミストが試算し、厚労省も同様の試算を示していた。 だが、今回約18兆円もの赤字を叩き出したことは、「新型コロナのせいなのだから仕方がない」などと済ませられるようなものではない。むしろ、国民が老後のために捻出してきた約18兆円もの年金を一気に溶かしてしまう、現在の運用システムの問題が浮き彫りになったというべきだ。 そもそも、GPIFは国民が積み立てた年金を資産運用し、その金額は130〜160兆円にものぼることから「世界最大の機関投資家」「クジラ」とも呼ばれる。だが、以前は国民の年金を減らしてしまう危険性を考え、株式などリスクのある投資を直接的にはほとんどしていなかった。 しかし、第二次安倍政権下の2014年10月に基本ポートフォリオを大幅に変更し、株式への投資を全体の半分にまで増やすことを決定。これは、GPIFに大量に株を買わせれば株価が上がり、景気が回復したという印象を与えることができるという安倍政権の計算があったためだ。 ようするに、国民の大事な年金を世論操作と政権維持に利用したわけだが、基本ポートフォリオを大幅変更したあとの2015年度には5兆3098億円の運用損を叩き出す結果となったのだ。 そして、2019年度は約8兆円もの赤字──。このように書くと、安倍政権支持者は「ほかの年は黒字だ」と騒ぐが、2015〜2019年度の黒字額は6兆8039億円だ。2020年1~3月期の約18兆円という損失額を見てもわかるように、今後も世界の新型コロナの感染拡大状況によって同じように株価市場に大きな影響が出る可能性は十分考えられる。株式投資割合を増やすという「大博打」後の黒字は一気に吹き飛び、それどころか赤字に転落することもありうるのである。 しかも、この年金を使った「大博打」による失敗のツケを払うのは、言うまでもなく国民だ。 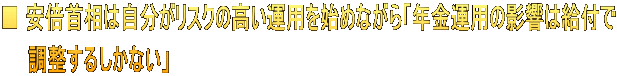 実際、安倍首相は国会でこう明言している。 「基本的に、年金につきましては、年金の積立金を運用しているわけでございますので、想定の利益が出ないということになってくればそれは当然支払いに影響してくる」 「給付にたえるという状況にない場合は当然給付において調整するしか道がないということ」(2016年2月15日衆院予算委員会) それでなくても株式の投資割合を半分にまで上げたこと自体が高リスクの大博打状態なのに、世界経済は今後、新型コロナの行方に左右されつづけることは間違いない。そして、このまま高リスクの投資に年金が注ぎ込まれつづければ、安倍首相が明言したように、わたしたちの年金給付額が減ってゆく事態になりかねないのだ。 安倍政権が「新型コロナの影響」と言えば国民は納得すると高を括っているのだろうが、問題の本質は、こうした危機の影響をモロに受け、一気に約18兆円もの年金を溶かしてしまう運用のあり方そのものにある。決して騙されてはいけない。 (編集部) 【出典】LITERA 2020.07.03 09:33
|
| 【出典】LITERA 2020.06.16 10:57 |
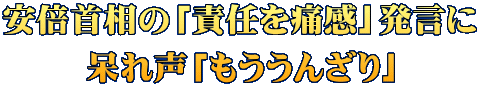 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
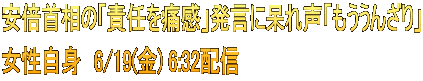 河井案里議員(46)と河井克行前法務大臣(57)が6月18日、買収の疑いで逮捕された。昨年10月、案里容疑者陣営の公職選挙法違反が報じられてから約8ヵ月。2人の逮捕が大きな波紋を呼んでいる。
毎日新聞によると2人は共謀して案里容疑者を当選させる目的で、19年に案里容疑者への投票や票のとりまとめなどの選挙運動を5人に依頼。その報酬として計170万円を供与したとされている。さらに克行容疑者は同年、91人に報酬として計約2400万円を供与したという。 「2人は昨年10月、いわゆるウグイス嬢に法定上限を超える報酬を支払ったという疑いが一部週刊誌で報じられました。克行容疑者は法務大臣を辞任する際に『説明責任を果たしていきたい』といったものの、その直後から2人は雲隠れ状態に。 国会を1ヵ月以上も欠席したにも関わらず克行容疑者は323万円、案里容疑者は194万円ものボーナスを満額でもらっていたため非難の声が相次いでいました」(全国紙記者) 各メディアによると、議員辞職をする意向ではないという2人。ネットでは《国民への説明はいっさいなかった》《お金返して欲しい》と厳しい声が再燃。また、その火の粉は自民党にも及んでいる。 「2人に選挙資金として1億5000万円にも及ぶ大金が自民党から振り込まれていたと発覚しています。そこには案里容疑者の対立候補であり、安倍晋三首相(65)に批判的な立場だった溝手顕正元議員(77)を落選させる意図があったのではないかとの指摘も。また、克行容疑者はもともと法務大臣。法務省の長であったにも関わらず、逮捕されるというのは憲政史上初のことです。そのため安倍内閣、ひいては自民党に厳しい視線が注がれています」(前出・全国紙記者) そんななか、各メディアによると18日に安倍首相はこうコメントしたという。 「我が党所属であった現職国会議員が逮捕されたことについては大変遺憾であります。かつて法務大臣に任命した者として、その責任を痛感しております」 「自民党総裁としてより一層襟を正し、国民に対する説明責任を果たしていかなければならないと考えています」 毎度のように「遺憾であります」「責任を痛感しています」と述べた安倍首相。ネットでは呆れたようにこんな声が上がっている。 《遺憾だとか責任は私にあるだとか、口先だけの会見はもう十分です。本当に悪いと思っていて、責任を痛感しているというのであれば、まずは具体的な説明責任を果たすべきでしょう。口だけで何もしないその姿勢には、もううんざりです》 《ただの不祥事と、違う。同時に2名が逮捕され、そのうち1名は自身が任命した法務大臣。「遺憾」や「襟を正す」では、済まない》 《「我が党所属であった現職国会議員が逮捕された」? 昨日まで自民党 だったじゃねえか》 【出典】女性自身 6/19(金) 6:32配信
|
| 【出典】LITERA 2020.06.16 10:57 |
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 新型コロナという「100年に一度の国難」(安倍首相)の只中にあるというのに、国権の最高機関であり唯一の立法機関である国会を、与党は明日、閉会させる見込みだ。 東日本大震災があった2011年、民主党政権は通常国会を8月31日まで延長し、9月と10〜12月に臨時国会を召集したが、新型コロナ対応にあたるいま、1年を通して審議がおこなわれるよう国会を開けておくことは当たり前の話だ。 しかし、安倍首相にはその「当たり前」が通用しない。安倍首相自身が「夏になったからと言って安心できない」などと第2波を懸念しているというのにどうして国会を閉じるのか、その理由はただひとつ、「追及を受けたくない」からだ。 世論調査では軒並み内閣支持率が下落しているが、これまでも安倍首相は国会閉会によって追及から逃げることで低下した支持率を持ち直させ、森友・加計疑惑や「桜を見る会」問題を有耶無耶にしてきた。 今回も同じように、新型コロナ対応の追及を封じ込めようというわけだ。 実際、いま国会が閉じてしまえば、追及がおこなえなくなる問題は山のようにある。 そのひとつが、電通への再委託が問題となっている「持続化給付金」だ。 事務を受託したサービスデザイン推進協議会をめぐっては入札に参加したデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社のほうが応札額が低かったことや、第二次補正予算に盛り込まれた「家賃支援給付金」でも支給事務をリクルートに約942億円という巨額で委託することが判明するなど、追及・検証が必要な問題が数々出てきている。 だが、さらに重要なのは、「申請から支給まで2週間程度」と謳われていた「持続化給付金」が、2週間以上経っても支払われていない人が数多くいるということだ。 しかも、申請開始の5月1日から11日のあいだに申請を受け付けた約77万件のうち、約5万件が1カ月経っても支給されていないというのである(6月12日時点)。 中小・零細企業にとって「命綱」であるこの給付金が1カ月経っても支給されない──。申請しているこの約5万件の事業者、そして雇用されている人たちのことを考えれば、どうしてこんなことになっているのか、安倍首相にはしっかり国民に説明する必要がある。 だが、安倍首相は15日の参院決算委員会で「この1カ月間で150万件に支払いをしている」「現場がぼーっとしていて何もやっていないのではまったくない」などと主張。 挙げ句、5月1日に申請した人たちにまだ支給されていない問題について、こんなことを言い出したのだ。 「申請する方もですね、人間ですから、これ、何にもまったく問題がなくて、受ける側がですね、受ける側が、全然、これ怠慢でですね、できてないというのでは、これは、これは明確に申し上げなきゃいけないんですが、それではないんですよ。そこをはっきり申し上げておきたいと思います。それはやはり、書類のなかにですね、さまざまな課題や、課題というか問題があったのは事実なんですよ」 「申請者に連絡を取ったら、また、なかなか(連絡が)つかなくなってしまった、あるいはまたですね、申請しても『こうこうこうしてください』と言っても、なかなかそうなってないのもあるんですよ、正直に申し上げまして」 「一人ひとり、相当ていねいに、これ、やっているんで、残ったのは少しですから。でも、それ以外は、これだけ進んでいるんですから、そこはですね、一生懸命やってるっていうことは評価もしていただきたいし、すべてがですね、経産省側の手落ちで、ということでもないわけであります」 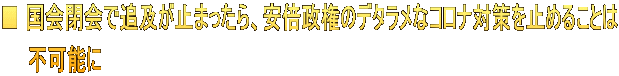 少なくとも約5万件もの事業者が1カ月も支給されないままにあることを「残ったのは少し」と発言すること自体が信じられないが、もっと酷いことに、申請者に対して「提出してきた書類に問題があった」「連絡がつかなくなった」「指示しても指示通りにしてこない」など一方的に文句をつけ、「経産省は一生懸命やっている。経産省は悪くない」と主張したのである。 国会で繰り広げられた、この絶句するような安倍首相の答弁。だが、重要なのは、国会は野党による追及によって安倍首相のこうした姿勢をあぶり出し、メディアがそれを報じ、国民が批判の声をあげて問いただすことができるということだ。 その機会が奪われるということは、独断専行の安倍首相の暴走や怠慢を直接、追及する場を失うということなのである。 実際、一律10万円給付にしても、国民が批判の声をあげた結果、安倍首相を方針転換させることができたが、いまだに全世帯の4割程度にしか給付されていない状況にある。さらに、10兆円という前代未聞の予備費がまたも隠れ蓑を通じて電通のような安倍政権に近い大企業に流れる可能性だって十分にある。 今後、国会が開かれなければ、こうした問題を安倍首相に直接追及することができるのは、安倍首相の気分で開催が決まる記者会見くらいになってしまうのだ。 国民の命・生活を守るための議論より自己保身を優先し、逃げることを「恥」とも感じていない安倍首相。 しかも、ここにきて河野太郎防衛相がイージス・アショアの配備計画の停止を表明したが、停止の理由であるブースターの落下地点の問題はこれまでさんざん指摘され、一方で政府は「安全に配備・運用できる」と説明してきたものだ。 当然、その説明の食い違いについて徹底追及されなければならないが、肝心の国会は閉会してしまう。つまり、追及を避けるために閉会直前のタイミングを狙って配備計画停止を打ち出したのではないか。 繰り返すが、このまま国会を閉じるということは、新型コロナの感染が再び拡大したときに新たな補正予算や立法を伴う対策や、またその追及もできず、これまでよりももっと杜撰な対応がとられかねないという危険な問題を孕んだものだ。 立憲民主党と国民民主、共産、社民の野党4党は年末までの国会延長を要求、閉会日となる明日にも国会に延長動議を提出するとし、Twitter上では「#国会延長を求めます」「#国会を止めるな」というハッシュタグが生まれている。 国民から背を向けようという安倍首相のトンズラを、けっして許すわけにはいかない。 (編集部) 【出典】LITERA 2020.06.16 10:57
|
| 【出典】LITERA 2020.06.16 10:57 |
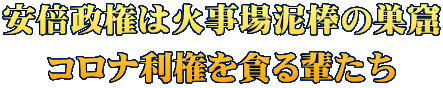 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
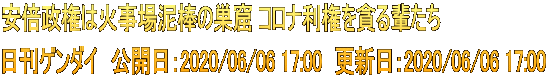 新型コロナウイルスが庶民生活を直撃している。内閣府が5日発表した4月の景気動向指数(2015年=100)速報値によると、景気の現状を示す一致指数が前月比7・3ポイント低下の81・5と大幅に悪化し、過去最大の下げ幅を記録。 総務省の家計調査(4月)でも、1世帯(2人以上)当たりの消費支出額が物価変動の影響を除く実質で前年同月比11・1%減少となり、比較可能な01年1月以降でやはり過去最大の落ち込みとなった。 発表される指標がことごとく悪化している原因は、言うまでもなく新型コロナの感染拡大に伴う外出自粛や緊急事態宣言によって経済活動が抑制されたことだ。 宣言が解除されたとはいえ、今後、雇用、給与、物価……など、あらゆる場面で庶民生活に深刻な影響が出てくるのは間違いない。いつまで続くのかみえない「コロナ禍」という“災害”によって、多くの国民が生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされる状況になりつつあるのだ。 この未曽有の危機を乗り越えるためには、与野党、官民の区別なく、すべての国民が英知を結集させて新型コロナ対策に取り組むべきなのは言うまでもないが、そんな非常事態下の中、国会ではコロナ禍に乗じて政府や企業が仲間内と結託し、こっそりと税金をかすめ取る動きをしていた問題が浮上している。 国が新型コロナの影響を受けた中小企業などに最大200万円を支給する「持続化給付金事業」をめぐる中抜き疑惑だ。 コトの概要はこうだ。「持続化給付金事業」の事務業務を約769億円で受託した一般社団法人「サービスデザイン推進協議会」(東京)が、業務の大部分を大手広告会社の電通に約749億円で再委託していたもので、野党らが「実際は何もせずに20億円を得るのは高額過ぎる」と批判の声を上げているのだ。 経産省は「給付金の振込手数料」(約15・6億円)、「人件費」(約1・2億円)、「旅費や事務用品費」(0・5億円)などと説明しているが、業務を右から左に流すだけでポンと20億円が手に入るのだから、協議会にとってこれほどボロい商売はないだろう。 協議会は16年に設立され、電通や人材派遣大手のパソナ、ITサービス業のトランスコスモスなどが関与したとされる。 1日現在の協議会理事はいずれも非常勤の8人で、この3社の関係者らが就任。「持続化給付金事業」を含めて経産省から14件、計1576億円の事業を受託し、うち9件は今回と同様、電通やパソナなどに再委託していた。 つまり、外形的に見れば、協議会は公共事業を受注する窓口の役割に過ぎず、実際は仲間内に流すだけの「トンネル団体」だということだ。 まさに濡れ手で粟のごとく「コロナ禍で丸儲け」という信じられない構図が浮き彫りになりつつあるわけだが、このコロナ利権に群がる怪しい輩たちの仲間に経産省も加わり、官製談合の疑いまで浮上してきたからクラクラする。 政治評論家の本澤二郎氏がこう言う。 「我々の税金を一体何だと思っているのか。本来であれば、ピンハネされるお金をもっと国民生活に使えたはずです。政府はコロナ禍で苦しむ国民のことなど、まるで考えていないのでしょう。あまりにふざけています」
梶山経産相は「持続化給付金事業」の中抜き問題について「手続き上の問題はない」と繰り返しているが、この問題は手続きうんぬんではない。 委託、再委託、さらに関連会社に業務発注……と仲間内で税金を分け合う構図が問題で、だから事業予算が膨らむ一方で、給付が進まないのだ。 本来は「トンネル団体」に委託するのではなく、全国に9カ所ある経産省の出先機関や地方自治体を活用すればいいのであり、そうすれば予算も低く抑えられ、給付の迅速化も図られたはずだ。 新型コロナ禍から国民生活を守るため、どうすれば「最小の経費で最大の効果」を上げることができるのか。 そういう発想が今の政府、行政に全くないことが病巣とも言えるのだが、公益よりも私利を優先するようになったのも、「政治の私物化」を当たり前のように行ってきた安倍政権の長期化が原因だろう。 とりわけ、お友達を厚遇してきた安倍政権の中で、“利権の権化”ともいわれているのが竹中平蔵東洋大教授だ。 竹中は政権主流の経産省の出向者が大半を占める「未来投資会議」のメンバーを務め、働き方改革の名の下で派遣法の拡大や残業代ゼロなどの政策を主導。 人材派遣のパソナグループ会長という顔も持つ竹中は「規制緩和」「民営化」と言って国民のためという形を装いながら、実際は“利益誘導”していたわけだ。 竹中は水道や空港などインフラの民営化も主張していたがその後、民営化された空港の運営を任されたのは竹中が関与していた企業だった。 今国会で成立した「スーパーシティ構想」(国家戦略特区法改正案)も旗振り役は竹中。政権の中枢で、これほど露骨にアベ友が利権を求めて闊歩している姿には呆れるばかりだ。 おそらく竹中みたいな利権を貪る輩が、今の政権内にまだまだ潜んでいる可能性は高く、表面化していないだけで「丸投げ」「中抜き」がゴロゴロしているに違いない。 9月入学や英語民間試験のドタバタを見ても分かる通り、教育すら利権がらみで政策判断するのが今の政権なのだ。まさに火事場泥棒の巣窟と言っていい。 新型コロナでPCR検査の数が絞られたのも、国立感染症研究所の検査権益や厚労省医系技官の利権を守るため――と言われているし、ワクチン開発だって製薬会社の利権がうごめいていると囁かれている。 事務局委託先の公募が急きょ中止されることが決まった観光需要喚起策「Go To キャンペーン」は「全国旅行業協会」の会長を務める自民党の二階幹事長の肝いりとされ、カジノ(統合型リゾート産業)や東京五輪は有象無象の利権屋が水面下で暗躍していると報じられてきた。詰まるところ、「持続化給付金事業」の中抜き問題は氷山の一角に過ぎないのだ。 次から次へとデタラメの悪事が露呈するものの、安倍政権は数の力をバックに知らんぷり。安倍首相は野党の国会質問を「意味がない」とまで言い切る始末だ。 長期政権ゆえのおごりから腐臭が漂い始めているのは明らかなのに、誰もチェックができず、やりたい放題。このまま悪辣政権をのさばらせたら何をしでかすか分からない。高千穂大教授の五野井郁夫氏(国際政治学)はこう言う。 「中抜き問題で、我々の血税を仲間内で回す仕組みという利権の構造がハッキリしたわけですが、そこには政治家だけでなく、官僚、大企業の癒着の構図もあらためて浮き彫りになりました。 この強固な政官財のトライアングルは、我々の税金をかすめ取り、甘い汁を今も吸い続けている。これは許せないし、一刻も早く壊すためにも政権の座から引きずり降ろさなければなりません」 国民は今こそ、怒りの声を上げるべきだ。 【出典】日刊ゲンダイ 公開日:2020/06/06 17:00 更新日:2020/06/06 17:00
|
| 【出典】日刊ゲンダイ 公開日:2020/05/25 14:50 更新日:2020/05/25 21:24 |
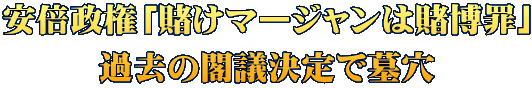 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
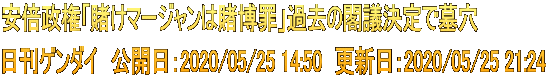 “官邸の守護神”黒川弘務前東京高検検事長が、緊急事態宣言下にもかかわらず「賭けマージャン」に興じていた問題で、安倍政権は末期状態だ。23日実施の毎日新聞の世論調査で支持率が27%と“危険水域”の20%台に下落。 4月8日の調査に比べ、マイナス17ポイントもの“暴落”だ。ツイッターでは、「#さよなら安倍総理」のタグ付き投稿が40万件を超える(24日夜7時時点)ネットデモも巻き起こっている。そんな中、安倍政権の「過去の閣議決定」がさらなる決定打となりそうだ。 ◇ ◇ ◇ 問題の閣議決定は、第1次安倍政権時のものだ。2006年12月8日付で、鈴木宗男衆院議員(新党大地=当時)が賭けマージャンを含む賭博の定義などについて、内閣に質問主意書を提出。週刊誌の投書欄に、外務省内部で違法賭博が行われていることを示唆する記述があったことを受け、〈(省内で)賭け麻雀を行ったという事例があるか〉とただし、「賭博」の定義や〈賭け麻雀は賭博に該当するか〉などと質問している。 安倍内閣は同19日付で回答。省内で賭けマージャンが行われていたか否かは〈確認できなかった〉としたものの、賭博の定義については〈偶然の事実によって財物の得喪を争うこと〉と刑法の記述を提示。 賭けマージャンについては、〈財物を賭けて麻雀【中略】を行い、その得喪を争うときは、刑法の賭博罪が成立し得るものと考えられる〉と、ハッキリと「賭博に該当」との見解を示している。 質問主意書に対する内閣の答弁書は、各府省などで案文を作成し、内閣法制局の審査を経て閣議決定された見解を、質問者が所属する議院議長に示すものと規定されている。つまり、安倍内閣は「賭けマージャンは賭博罪」と、金額に関係なく違法であることを閣議決定していたわけだ。 ところが、22日の衆院法務委で、法務省の川原隆司刑事局長は、黒川氏が参加した賭けマージャンのレートについて、1000点当たり100円の「点ピン」だったと示した上で「必ずしも高額とは言えない」と、悪質性を打ち消す答弁を展開。懲戒処分もせず退職金を満額払う。過去の政府見解と矛盾するのは明らかだ。 こんなデタラメだからだろう。SNSでは「堂々と賭けマージャンしよう」という呼びかけが広がっている。 ツイッターでは、「【祝レート麻雀解禁!】検察庁前テンピン麻雀大会」と題し、参加者を募集する人まで現れた。「1000点100円=黒川レート」なんて言葉も出現している。皮肉を込めたイタズラかもしれないが、参加者に「政府は黒川レートならOKなんでしょ」と反論されたら、捜査機関はどうするのか。 「法律自体は、宗男議員が質問した06年と現在で変わっていないのに答弁は正反対。その矛盾を野党に質問されたらどう答えるのでしょうか。安倍政権は、これまでも自らや“お友達”を守るため、法の趣旨や過去の政府見解をねじ曲げてきました。この『一貫性のなさ』は今度こそ徹底的に追及されなければなりません」 (高千穂大教授の五野井郁夫氏=国際政治学) 黒川問題はまだ終わっていない。安倍首相は墓穴を掘った。自ら「さよなら」を切り出す時だ。
大甘処分の“犯人”はやはり安倍官邸だった。 賭けマージャンで辞職した黒川弘務前東京高検検事長の処分について、法務省は国家公務員法に基づく「懲戒」に当たると判断したのに、官邸が懲戒にはしないと結論付け、法務省の内規に基づく「訓告」となっていた。複数の法務・検察関係者が証言したと、24日、共同通信が報じた。 安倍首相は22日、国会で訓告より重い懲戒にすべきだと追及されたが、「検事総長が事案の内容など、諸般の事情を考慮し、適切に処分を行ったと承知している」と繰り返し、責任を法務省に押し付けた。 しかし、法務・検察関係者によると、事実関係を調査した法務省は、賭博をした職員は「減給」または「戒告」の懲戒処分とする人事院指針などに照らし、懲戒が相当と判断。任命権者の内閣として結論を出す必要があると考えていた。 森雅子法相は21日午前、報道陣に「21日中に調査を終わらせ、夕方までに公表し、厳正な処分も発表したい」と発言。この後、官邸と詰めの協議をし、官邸側の意向で訓告になったという。 ある法務・検察関係者は「当然、懲戒だと思っていたので驚いた」と証言した。
【出典】日刊ゲンダイ 公開日:2020/05/25 14:50 更新日:2020/05/25 21:24
|
| 【出典】日刊ゲンダイ 公開日:2020/05/25 14:50 更新日:2020/05/25 21:24 |
 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
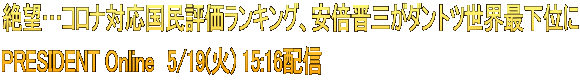 「コロナで死ななくても、収入が絶たれて死ぬよ」
ポツリとそうつぶやく自営業の男性がTVに出ていた。同様の溜め息がいま日本全国に広がっている。4月7日発令の「緊急事態宣言」はさらに延長され、十分な補助や補償がないまま4月をなんとか耐え忍んだ中小企業や個人事業主、非正規雇用者などが、次々に廃業、解雇、雇い止めに追い込まれている。 中国が武漢のロックダウン(都市封鎖)を行ったのが今年の1月末。3月には欧州各国が相次いでロックダウンを実施し、同時に休業補償等も速やかに行うなか、日本では5月半ば現在、いまだ10万円の給付金はおろか、首相肝いりの「アベノマスク」2枚すら全国民の手元に届いていない。首相お気に入りのフレーズ「スピード感」は、いったいどれくらいの速度をイメージしているのだろうか。 そんな怒りとも嘆息ともつかない国民感情を反映する数値が、この度、海外の調査会社によって明らかになった。シンガポールの調査会社ブラックボックス・リサーチとフランスのメディア会社トルーナが、共同で行った意識調査だ。 両社による「自国のコロナ(COVID-19)対応への満足度」調査では、ほとんどの国が自国のコロナ対応に不満足を抱いていることがわかったが、なかでも注目すべきは日本の満足度のずば抜けた低さだった。 23の国と地域に住む約1万2600人(18~80歳)を対象に行われたこの調査の質問項目は全部で4つだ。「政治的リーダーシップ」「企業のリーダーシップ」「地域社会」「メディア」の4分野における世界の総合平均点は100点満点中、45点だった。 それに対して日本の総合スコアは16点という驚異的な低さ。「政治的リーダーシップ」分野にいたっては、世界平均40点のところ、驚きの5点だった。見事な赤点ぶりというほかなく、当然のことながら順位は「政治リーダーシップ」でも総合でも、23カ国・地域の中でダントツの最下位だった。 以下、調査結果を詳しく見ていこう。 ランキングのトップに輝いたのは、総合分野で85点を記録した中国だ。4つのカテゴリーすべてでもっとも国民の満足度が高い結果となった。2位はベトナム(77点)、3位はアラブ首長国連邦とインドが同じ59点と続く。 西洋諸国のなかで総合点が平均の45点を上回ったのは、ニュージーランド1国のみ。アメリカ・オーストラリア・イタリア・ドイツ・イギリス・フランスはすべて平均点以下で、特にフランスは西欧諸国内で最下位、23カ国・地域全体でも下から2番目の順位に甘んじることとなった。 さて、この結果をどう見るべきだろう。調査結果は「〈西洋圏〉のほうが〈アジア圏〉よりも自国満足度が低い傾向にある」ことを示している。 その理由の一環としては、「アジア主要国は、過去に流行したSARS(重症急性呼吸器症候群)やMERS(中東呼吸器症候群)などの経験があり、ふたたび同様の呼吸器系疾患が蔓延しても、自国政府は必要な手段を講じるはずだと信じているから」だと述べられている。 たしかにその点、幸運にも過去の新型コロナウイルスの影響を受けることがほどんどなかった日本やアメリカ、そして西欧諸国は、今回のパンデミックに対しても心の準備ができていなかったといえる。 中国武漢で感染爆発したときも、どこか対岸の火事として眺めていた節がある。まさか“先進国”たるわが国の医療体制がここまで壊滅的打撃を受け、政治や経済が混乱することになるとは専門家以外は実感していなかったのだろう。 「フランス人の84%が、指導者のコロナ準備対応が遅すぎると感じており、日本の82%、アメリカの74%の国民も、同様の思いを抱いている」と調査報告は続ける。 それにしても中国の点数が異様に高いことが気になる。ブラック・ボックスの創業者兼最高経営責任者のディビッド・ブラック氏は、中国に関してこのような指摘をしている。 「ほとんどの国が自国民の期待にうまく応えられていないなかで、唯一の例外は中国だ。それは世界がいまだコロナの感染爆発から抜け出せていないなか、中国だけがコロナを抑え、すでに次のフェーズへと歩みだしているからだ。中国政府はうまくこの危機を乗り切ったと国民が感じていることの証しである」。 たしかにこの調査が行われた時期が4月3日~19日だったことを考えると、その分析もうなずける。ただ、上位2カ国の中国とベトナムは、共に社会主義国家でもある。都市封鎖や行動制限の厳格さは、他の国々よりも徹底して行うことができたし、また言論の自由という意味でも、他国と単純に比較することができるかは不明な点も多い。 実はコロナウイルスが中国で蔓延しはじめた2月初め、私は中国人の知人に「マスクは足りているか」とSNSを通じてメッセージを送ったことがある。だが、普段ならすぐに返事が来るはずなのに今回はノーレスポンス。 返事が来たのは2カ月後の4月1日だった。メッセージには「中国ではこの間、SNSが禁止されており返事ができなかった」とサラリと書かれてあった。 現在、中国はコロナウイルスが武漢発祥であることの打ち消しに躍起になっている。危機を乗り越え、他国を援助できる力強い国としてのイメージ戦略にも奔走していることなども、考慮に入れるべきだろう。 ただ、そういったことも、日本のランクが最下位であることの言い訳にはならない。「世界中の国民が自国リーダーの手腕に期待しているが、それに成功して50点以上を獲得できているのは7カ国のみ。ランキング最下位の日本の場合は、わずか国民の5%しか政治のリーダーシップに満足していない」(調査報告)からだ。 日本についての分析はさらにこう続く。 「日本の低評価は、緊急事態宣言の発令が遅れたことや、国民が一貫して政権のコロナ対策を批判している現実とも合致している。明らかに日本国民は政治のリーダーシップに不満足であり、安倍政権はこのコロナ危機(という負荷の状態)において、(政治が正常に機能していないと見なされ)リーダーシップのストレステストに合格しなかったのだ」(ブラック氏)
しかも、改めてよく考えてみよう。今回の調査対象にはイタリアやスペイン、フランスやアメリカなど感染爆発により医療崩壊を起こした国々も多く含まれているのだ。命の選別トリアージが行われ、死者が続々と一時遺体安置室と化した大型冷蔵車に運び込まれ、葬式も出せず埋葬されていく光景を、私達もTV画面を通じて痛ましい思いで眺めていたはずだ。 一方の日本はそこまでの惨状にはギリギリ至っていない。たしかに、いまだPCR検査数が他国に比べて圧倒的に少ないため、そもそもの感染者数が厳密には把握しきれていないという指摘もある。急激な体調悪化で救急車搬送されるも、何十軒もの病院に受け入れを拒否されたという人もいる。 それでも5月12日時点の公式発表では、コロナ感染者数は1万6024人で、死亡者数は691人だ。誤差は存在していても、少なくともアメリカの感染者数130万人超え、死亡者数8万人超えの規模に比べたら雲泥の差だ。 それでも、日本の国民は政権のリーダーシップに満足していない。ブラック氏は、「ほとんどの政権にとって今回のパンデミックは前例がなく、いまだ予期せぬ事態に振り回されている」とコメントしているが、日本の場合は、それ以前の問題かもしれないのだ。 それはたとえば、首相自ら「PCR検査を1日に2万件に増やす」と宣言しておきながら1カ月後にも同じことを言っている現実や、「かつてない規模」の「あらゆる政策を総動員」した「大規模な対策」の結果が、まさかの「1世帯2枚の布マスク」であることの衝撃、しかも予算466億円を見積もって届いたマスクがカビだらけだったことの情けなさ、そもそもその予算や発注先も不明瞭な点が多々あることへの不信感など、国民の間に横たわる不安感や絶望感が影響しているのではないだろうか。 今回、西洋諸国でトップに立ったニュージーランドは、「感染拡大の抑え込みに成功し、ジャシンダ・アーダーン首相のリーダーシップは国民から高い評価を受けている」と、ブラック氏から評されている。 かの国の「政治的リーダーシップ」は67点。最下位の日本の5点とは比較にならないが、いったいその差はどこにあるのだろうか。 アーダーン首相は笑顔が魅力的な39歳の女性である。だが、美人であるだけではもちろんない。観光国にもかかわらず3月19日時点でいち早く外国人旅行者に対して国境封鎖を行うなど、大胆な決断力と行動力を持っている。 その一方で、オフタイムにはスエット姿で自宅からSNSに登場し、気さくに国民からの質問に応える柔軟性も持つ。国民を「500万人のチーム」と呼び、メッセージの最後には必ず「強く、そしてお互いに優しく」と語りかける人間的な親しみやすさが伝わってくる。 翻って日本だ。幸か不幸か、自粛生活で日中にTVを観る人が増え、リアルタイムで国会中継を観る人が増えた。そこで私たちが目にしたのは、カンペがないと目が泳ぎ、事前報告がない国会答弁には、キレまくる首相の姿だった。 しかも、コロナ危機という「緊急事態」の裏で、「検察庁法改正案」を押し通そうとする姿勢には、たった数日で400万件以上の「#検察庁法改正案に抗議します」ツイートが国民から発せられた。両者の差は歴然である。 もっとも「政治的リーダーシップ」以外の分野でも、日本の課題は多い。「コロナ危機において、企業はより積極的な役割を果たすべき」と考えている人は多く、調査対象の82%の人々が、少なくとも「上場企業は最低限の貢献を社会になすべき」だと感じているからだ。 そうしてみると、日本の「企業リーダーシップ」が6点(世界平均28点)というのは、残念な数値だ。その他、「地域社会」が6点(世界平均37点)であることも、「自粛警察」が他者を批判する事例が続出する日本ならではの数値かもしれない。 ブラック・ボックスの調査報告の最後は、このように締めくくられている。 「パンデミックで私たちの世界観は劇的にシフトしていくでしょう。政府のあり方、ビジネス手法、健康医療分野においても。コロナウイルスは人類にとって最初で最後のパンデミックではなく、各国のトップは今後もさらなる政治の舵取りや危機インパクトを熟考していく必要があります」。それこそが国民の信頼の回復につながるとつづっているのだ。 三浦 愛美(みうら・まなみ) フリーランスライター 1977年、埼玉県生まれ。武蔵大学大学院人文科学研究科欧米文化専攻修士課程修了。構成を手がけた本に『まっくらな中での対話』(茂木健一郎ほか著)などがある。 【出典】PRESIDENT Online 5/19(火) 15:16配信
|
 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
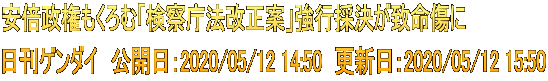 安倍政権がコロナ禍のドサクサに紛れてゴリ押しする検察庁法改正案がモーレツな批判にさらされている。新型コロナウイルス対応は後手後手なのに、検察官人事の恣意的運用の正当化は超特急だからだ。週末から「#検察庁法改正案に抗議します」のハッシュタグをつけたツイートが急増。著名人も次々に参戦し、500万件を超えてツイッターデモ化しているが、アベ自民党はお構いなし。週内の衆院通過をもくろんでいる。しかし、採決を強行したら命取りになるだけだ。 安倍政権が、検察官の定年を延長する「検察庁法改正案」の成立にシャカリキになっているのは、「官邸の守護神」と呼ばれる黒川弘務東京高検検事長を検事総長に就任させるためだ。 そもそも問題の発端は、本来“2月退官”だった黒川検事長の定年を、1月末の閣議決定で半年間延長したこと。今回の法案は、官邸の脱法行為を後付けで正当化しようというものだ。しかも、国家公務員の定年を65歳に延長する国家公務員法改正案と抱き合わせにして、8日の衆院内閣委員会で審議入りした。 検察庁法改正案に反対する野党は、森法相の出席や内閣委・法務委の連合審査を求めたが、与党は森法相の出席を拒否。野党が欠席する中、与党と日本維新の会の3党のみで質疑を進めたのである。 こうした動きに芸能界も反発。きゃりーぱみゅぱみゅ、水原希子、城田優、井浦新、ハマカーン神田らが「#抗議します」のハッシュタグでツイートし、社会現象となっている。500万のツイートは、前代未聞である。 11日の参院予算委員会の集中審議で立憲民主党の福山哲郎幹事長がツイッターデモを取り上げ、検察庁法改正案の分離を提案したが、安倍首相は「政府としては法案として提出させていただいている。どのような議論を行うかは国会でお決めいただきたい」とスッとぼけた。 「週内の衆院通過は既定路線。8日の内閣委で2時間審議したのを踏まえ、13日には残り3時間を質疑に充てて採決する方針です。野党が求める森法務相の出席には応じない」(与党関係者) 安倍政権は、なにがなんでも息のかかった人物を検事総長に就けるつもりだ。オトモダチ政治をあらわにした「モリカケ疑惑」も、地元の票集めに利用してきた「桜を見る会疑惑」もチャラにしようというのである。 「#抗議します」に賛同した元特捜検事の郷原信郎氏は言う。 「日本の司法は検察が公訴権を独占している。政権が検察の人事を支配するのは三権分立を揺るがす大問題ですし、法務省と関係ないところで審議しているのもメチャクチャ。そもそも、検察官の職務は属人的ではなく、定年延長は全く必要ないし、そうした要望もない。にもかかわらず、政権が強行するのは邪な目的からにほかならない。違法な閣議決定を数の力で正当化しようとしている」 一方、アベ応援団は理屈で反論できないのか、「#抗議します」をツイートした芸能人に「法案を理解していない」「政治的な発言をするな」とイチャモンをつけ、「#検察庁法改正案に興味ありません」というハッシュタグまで出現している。 しかし、500万ツイートを無視したら、火に油となるだけだ。これまでは、どんな悪法も成立してしまうと国民の怒りは沈静化した。ところが、今回の法改正には、有名人が「もうこれ以上、保身のために都合よく法律も政治もねじ曲げないで下さい。この国を壊さないで下さい」と切実に訴えている。かつてない大きなうねりを踏みつぶせば、政権の致命傷になるのは必至である。 【出典】日刊ゲンダイ 公開日:2020/05/12 14:50 更新日:2020/05/12 15:50
|
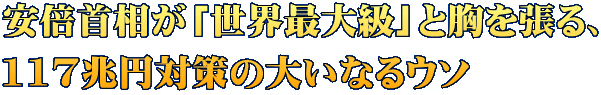 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 <安倍政権が打ち出したコロナ危機への経済対策は、表面的な金額こそ立派だが、その中身をひもとくと問題が山積している> 政府は新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため、総額117兆円の緊急経済対策を取りまとめた。だが、支援の実施方法や金額に関して多くの批判が寄せられている。 率直に言って今回の対策は、直面している危機に十分な効果を発揮するとは思えない。 「関連記事」 【チャートで見る】コロナ失業のリスクが高い業種 世論の批判を受けて安倍首相は、世帯を限定して30万円を給付するプランを撤回し、個人に対して一律10万円を支給する施策に変更した。広範囲な給付に切り替わったことは評価してよいが、課題は山積している。 安倍政権は4月7日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策を閣議決定した。事業規模の総額は108兆円とGDPの2割を突破している。これはアメリカやドイツに匹敵する水準で、表面的な金額としては過去最大といってよい。だが、この施策には大きな問題があり、このまま実施した場合、十分な効果を発揮しない可能性が高い。 安倍首相は117兆円という金額について「世界最大級」と胸を張るが、これは事業規模の総額であって、実際に政府が財政支出する金額ではない。 企業に対する納税や社会保険料の支払い猶予(約26兆円)は、あくまで一時的な猶予にすぎず、資金繰り支援に使われる財政投融資(約10兆円)についても、基本的には貸し付けなので返済が求められる。 さらに言えば、昨年12月に閣議決定した26兆円の経済対策のうち、まだ執行していない分(約20兆円)や、3月までにまとめた緊急経済対策の第1弾と第2弾の分(約2兆円)など、今回の支援策と無関係なものまで含まれている。 政府は各支援項目の詳細を明らかにしていないが、「真水(まみず)」と呼ばれる政府が実際に支出する金額は18兆円程度、コロナ終息後に実施する旅行券配布などの施策を加えても28兆円程度と推定される。約47 兆円を真水とする政府の説明とは大きな乖離がある。 政府が撤回した30万円給付プランの最大の問題点は、給付条件をあまりにも厳しすぎたことである。基本的には住民税非課税水準に収入が落ち込まないと給付されない仕組みだが、中間層の世帯はほとんど支払い対象にならない。 政府は1300万世帯が給付対象になると説明していたが、もしこのプランが実際に発動された場合、給付対象となる世帯はもっと少なかっただろう。 一連の施策は閣議決定されたものであり、行政運営上、閣議決定の意味は重い。閣議決定を覆して10万円支給に切り換えたことは素直に評価してよいと筆者は考える。 だが、真水部分が少ないなど、この施策には依然として問題が多く、経済の落ち込みに対して十分な効果を発揮しない可能性が高い。 一方で、支出の詳細項目が定められておらず、資金の使途はある程度、自由になる余地も残されている。 今は、補正予算を成立させることが最優先だが、この法案を成立させた後、給付金以外の資金使途についても、給付金と同様、柔軟な決断を行っていく必要がある。 今の日本は、輸出で経済を成り立たせているのではなく、既に消費主導型経済になっている。消費は経済のエンジンであり、個人の経済状況が悪化すれば、日本経済そのものが立ち行かなくなる。 賃貸住宅に住んでいる場合、当座、10万円の支給があれば何とかなった世帯でも、家を追い出されてしまえば、その金額で生活を立て直すことは極めて難しい。ひとたび消費が壊れてしまうと、再構築するのは容易なことではない。 今後の経済対策についても、個人の生活を破綻させないことを主軸に、各種のプランを検討することが重要である。個人の生活を守ることは「福祉政策」ではなく、れっきとした「経済政策」であるとの認識が必要だ。 <本誌2020年4月28日号掲載のものを一部変更・加筆> 加谷珪一(経済評論家) 【出典】ニューズウィーク日本版 4/23(木) 12:21配信
|
 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
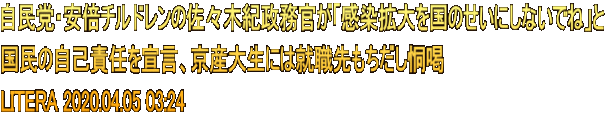 新型コロナの感染拡大にともなって、国民に自己責任を押し付ける安倍政権の姿勢が次々明らかになっているが、そんななか、政府の役職を務める自民党議員がとんでもないツイートをしていたことがわかった。 4月4日、国土交通大臣政務官を務める佐々木紀衆院議員が「外出自粛でも「買い物・旅行」、60代が最も活発」というニュースをリツイートしたうえ、こうツイートしたのだ。 〈国は自粛要請しています。感染拡大を国のせいにしないでくださいね〉 佐々木議員は、2012年の衆院選で引退した森喜朗元首相の後継として石川2区から出馬して当選、現在は細田派に所属する典型的な安倍チルドレン、しかも魔の3回生だ。 その思想はもちろん、ゴリゴリの極右で、日本会議国会議員懇談会、神道政治連盟国会議員懇談会、靖国神社に参拝する国会議員の会、さらには例の百田尚樹を招いて言論弾圧を語り合った文化芸術懇話会にも参加している。 しかし、それにしても、今回のツイート、ひどすぎないか。新型コロナ感染拡大で国民に不安が広がっているなか、これでは「国は自粛要請したんだから、あとは知らない、お前らの責任だ」と言っているようなものではないか。 当然、このツイートは大炎上。佐々木政務官はきょう5日朝になって削除し、こうツイートし直した。 〈国は自粛要請しています。感染拡大を国だけの責任にしないでくださいね。でも、自粛を求めるなら補償とセットでないといけません。しっかり取り組みます!〉 そして、すぐ後にこんな釈明をしている。 〈朝から、お騒がせいたしました。政府発表と強制力の弱さから、各個人の注意喚起の意味と行動を促す為の投稿でしたが不適切でした。4月7日には経済対策を出します。単発ではなく、必要に応じて対策を出していきますので、ご意見いただければと思います。〉 しかし、これ、炎上したから取り繕っているだけで、佐々木政務官の本音は完全に最初のツイートのほうであり、“コロナは国民の自己責任“というものだろう。というのも、佐々木政務官が感染者の責任をもちだしたのは今回のツイートがはじめてではないからだ。それどころか、3月30日には、コロナウイルスの感染者を犯罪者扱いするようなツイートも行なっている。 佐々木政務官はこの日、ヨーロッパ旅行に行っていた京産大生の感染が石川県で確認されたというニュースをリツイートして、〈卒業旅行みたいだけど、卒業後はどこに入社するのかな…その会社の対応が気になります。〉と投稿。 その数十分あとにも、富山県で京産大生の感染が確認されたというニュースをリツイートして、今度は〈3月にスペイン旅行って… また卒業旅行みたいだけど、卒業後は、どこに入社する予定だったのかな⁈〉とつぶやいたのだ。 これ、明らかに「こんな時期にヨーロッパに行くような学生を、企業はそのまま入社させるのか」という脅しだろう。 ヨーロッパ旅行で感染した京産大生は、ネットでもネトウヨなどからひどいバッシング浴びせられているが、彼らが旅行に出かけた時点では、ヨーロッパの感染者は日本より少なく、誰もこんな事態になるとは予想していなかった。 どういう条件下で感染したとしても感染者が糾弾されるというのはおかしいが、京産大生がヨーロッパ旅行に出かけたことについては、もっと批判されるいわれがない。しかも、富山県で感染が確認された京産大生については、ゼミの卒業祝賀会に参加していたというだけで、スペイン旅行に行ってたいたかどうか自体、報道されていない。 ところが、佐々木政務官は感染の発端となった京産大生がヨーロッパ旅行をしていたことを徹底的にあげつらい、就職先の問題まで持ち出して、脅しあげているのだ。これではほとんどネトウヨとかわりがないではないか。 いや、ネトウヨより悪質だ。というのも、ヨーロッパなどからの帰国者から感染が広がっている背景には、政府の検疫体制のザル状態が背景にあるからだ。空港の検疫所は厚生労働省の管轄だが、佐々木議員が政務官を務める国交省も協力体制をしくべき関係にある。 それこそ、帰国者任せになっている隔離のための滞在施設や交通手段の確保など、国交省の役割だろう。それなのに政府の責任は頰かぶりして、若い大学生に責任を押しつけているのだから、卑劣というしかない。 だが、この卑劣さは佐々木政務官だけのものではない。安倍政権のコロナ対応全体にいえることだ。検査体制も治療体制も整えず、感染の実態を隠し、感染拡大が明らかになったら今度は「自覚のない若者」や「夜の繁華街」のせいにする。 一方では、この期に及んでも、国民全員に必要なものを届ける即応的な生活支援も全く打ち出そうとしない。 それは結局、いまの自民党や安倍政権が佐々木政務官のような思想の持ち主の集合体だからである。そして、その頂点にいて、極右自己責任論者をどんどん公認候補に立ててきたのが安倍首相なのだ。 「感染拡大を国のせいにしないでくださいね」と口に出していないだけで、安倍首相も考えていることはきっと同じである。 (編集部) 【出典】LITERA 2020.04.05 03:24
|
 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
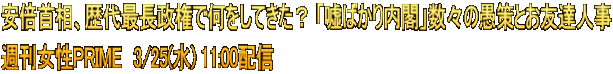 「7年間という長期政権で安倍さんは権力を持ちすぎてしまった。安倍さんを守るために官僚も大臣も平気で嘘をつき、国民ではなく安倍さんのための政治になっている」 山井和則衆院議員は第2次安倍政権をそう批判する。 通算すると歴代最長の長期政権となり、権力を恐れる周囲は“忖度”をしていく。その様子を“まるで戦前の日本だ”と評する人もいるが、この異常な状況はいつから始まったのか。アベノミクスならぬ“安倍の愚策”を振り返る。 次から次へと政策の看板をかけ替える 「安倍さんは20年にわたるデフレからの脱却を至上命題として掲げ、これを実現するために“金融緩和”“財政出動”“成長戦略”という三本の矢を打ち出しました。株価が上昇して一見、成功しているように見えたアベノミクスですが、実際はそんなことはありません。株価対策として年金資金が80兆円以上も使われているのです」 と、ジャーナリストの須田慎一郎さんがアベノミクス成功の目くらましを解説。続けて、こう批判する。 「安倍さん同様に長期政権だった小泉(純一郎)さんは、5年半の任期中に郵政改革を、中曽根(康弘)さんは5年で国鉄民営化、佐藤栄作さんは7年半で沖縄返還を実現しました。政策のよい悪いは置いておいて、実際に掲げた目標はそれぞれ達成しています。じゃあ、安倍さんは何をしたの? というと標語を発表するばかりで、達成できたのか検証もないまま次から次へと政策の看板をかけ替えている」 これまで安倍首相が掲げた標語は、 《デフレ脱却/三本の矢/女性活躍/地方創生/一億総活躍/働き方改革/人生100年構想/人づくり革命》 などといったもの。 「どれも聞きざわりのよい言葉ですが、例えば“人生100年構想”は定年を70歳まで延長して、さらに年金の普及を遅らせる狙いがあります。 “働き方改革”は電通の新入社員だった女性が長時間労働で自殺した事件や過労死が取りざたされ急きょでてきたスローガンです。長時間労働の是正や非正規社員の待遇改善がなされるのかと思いきや、現場企業を混乱させただけで9割の企業が働き方改革に成功していない(クロスリバー調べ)と答えています」(政治評論家の有馬晴海さん) 「安倍さんがしたことで、最も許せないのは憲法9条の法解釈を変えて集団的自衛権を合憲とし、自衛隊が専守防衛の枠を超えて武力行使できるようにしたこと。戦争に巻き込まれる国になったんです。大事なことなのに審議を尽くさず数の力で押し切っていく。まさに“独裁政治”です」 と、前出の山井議員。そんな“独裁”は数々の犠牲者を生んできた。 安倍昭恵夫人の関与が囁かれ、国有地が大幅に値引きして売却された森友学園問題。 「籠池夫妻は昭恵さんと出会わなかったら逮捕されなかった。ほかにも赤木俊夫さんという方が犠牲に。彼は財務省近畿財務局の上席国有財産管理者という立場で、文書改ざんを強いられ自殺されました。改ざん前の文書には昭恵夫人の名前が繰り返し出ているのに、安倍さんが国会で“私や妻が関係しているということになれば、間違いなく総理大臣も国会議員も辞める”と言い放ったことが文書改ざんの引き金です」(山井議員) さらに52年間どの大学も認められなかった獣医学部を新設する『国家戦略特区』の指定について官邸の働きかけがあったとされる加計学園問題。いずれも周囲が安倍首相に“忖度”し、起きたこと。 なぜ安倍首相の“独裁”が続くのか。前出の山井議員は、 「安倍さんの意向に逆らうものは冷遇され、従うものは好待遇を受けるというお友達人事があるからです。 例えば、与党内でも安倍さんに批判的だった溝手(顕正前参院議員)さんは、同じ選挙区に河井案里議員をぶつけられました。河井さんには1億5000万円もの選挙資金が投入され、溝手さんは落選。溝手さんを落としたことで夫の河井克行さんは法務大臣にまで出世しました」 と、お友達優遇人事を批判する。しかも案里議員は、その選挙で公職選挙法違反を疑われ夫は法相を辞任。先日ついに夫妻の秘書が逮捕された。 山井議員は続けて、 「森友問題だって、自殺された赤木さんの上司の佐川局長は出世しています。安倍内閣では安倍さんのほうを向いて嘘をつけば出世できるから、みんな言いなりになる。これまで20年近く議員を務めていますが、こんなに嘘ばかりの内閣は初めて! お友達議員は大臣にふさわしくなくても次々に出世。口利き問題の甘利明さん、防衛省をあれだけ混乱させた稲田朋美議員も守りました」 ほかにも“お友達記者”の山口敬之氏によるレイプ事件。 「山口氏に逮捕状が出たにもかかわらず官邸の鶴のひと声で取り下げられたと言われています」(全国紙社会部記者) 昨年から今年にかけても、公費の私物化が問題視された “桜を見る会”問題や、検察幹部の定年延長人事への介入問題など続々と疑惑が。 いつまで国民はこの“独裁”に振り回されるのだろうか。 「順調にいけば、東京五輪を花道にして来年9月の満期まで首相を務める予定だったと思います。しかしコロナでの対応が後手にまわり、反感情は高まるばかり。ある婦人団体は自民党に“一刻も早く総理をお辞めになってください”と手紙を出したそうです」(前出の須田さん) ツイッターでも『安倍辞めろ』というハッシュタグがトレンド1位になったが、数時間後には圏外になるという不思議な現象が起きた。 「絶対的権力は絶対的に腐敗する」(イギリスの格言) 忖度国家に警鐘を鳴らすのにぴったりの言葉だろう。
■2012年 12月 第2次安倍政権スタート ■2013年 12月 特定秘密保護法を強行、国民の“知る権利”が脅かされることに ■2015年 3月 安倍政権を批判していた元経産省の古賀茂明氏はレギュラー出演していた『報道ステーション』を降板させられたとし、自身の最終出演回に「I am not ABE(私は安倍首相ではない)」と書いた手製のパネルを掲げた 6月 安倍首相の元番記者の山口敬之・元TBSワシントン支局長に出されていた準強姦逮捕状を握りつぶす(伊藤詩織さんレイプ事件) 9月 集団的自衛権の一部行使容認を含む安全保障関連法が成立 ■2017年 2月 国有地売却をめぐる森友学園問題が発覚。首相の妻・安倍昭恵氏の関与が焦点に 5月 獣医学部新設をめぐる加計学園問題で「総理のご意向」文書が発覚 6月 共謀罪法を強行 ■2018年 3月 森友問題で財務省の公文書改ざんが発覚 12月 沖縄・辺野古への米軍新基地建設で埋め立てを強行 ■2019年 7月 衆院選で改憲勢力3分の2を割るも与党過半数を維持/安倍首相に批判的なことを言った一般人が複数の警察官に取り囲まれる事態に 11月 桜を見る会問題が発覚/'16年当時に安倍首相の元秘書の子息とトラブルを起こした相手が暴行容疑で逮捕されていたことが発覚(通常なら口頭注意ですむようなケンカだったと言われる) ■2020年 2月 従来の法解釈を変更し、東京高検の黒川検事長の定年を半年延長。官邸に近い黒川氏を次の検事総長にするため!? 3月 コロナで小中学校一斉休校要請 新型コロナ対策特別措置法施行 【出典】週刊女性PRIME 3/25(水) 11:00配信
|
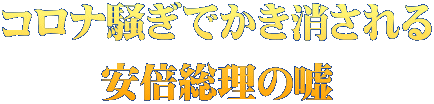 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
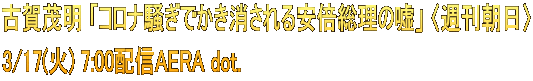 東日本大震災から9年。 被災地では、高速道路や鉄道などが再開した。公共事業も進捗し、物的なインフラは、時間とともに確実に回復してきた。 しかし、東京電力福島第一原子力発電所の事故処理は終わっていない。廃炉作業、汚染土・汚染水処理などは、遅々として進まず、終わりの見えない状況だ。 いまだに避難している住民も、大本営(政府)発表の数字でも福島中心に4万7千人。帰還したくてもできない地域は残されたまま。今さら故郷に戻れないという人も日に日に増える。 一方、そんなこととは関係なく、「復興五輪」と銘打った東京五輪の聖火リレーが来週から始まる。その起点は、福島県楢葉町・広野町にあるJヴィレッジだ。その後の聖火リレーの中継点も、事故の傷痕など感じさせない、きれいに整備された区域が中心だという。世界に「復興」をアピールする「だまし絵」だ。 思えば、東京五輪は、2013年9月のブエノスアイレスで開かれたIOC(国際オリンピック委員会)総会での安倍総理の歴史的な大ウソによって誘致された。福島原発事故から2年半後の当時、事故のインパクトは大きく、「東京」五輪といっても、「放射能は大丈夫か」と各国関係者や選手たちは心配した。 そこで、安倍総理は一世一代の賭けに出た。すぐにバレてしまうような嘘の演説で、各国を「説得」しようとしたのだ。 「フクシマについてお案じの向きには、私から保証をいたします。状況は、統御されています(アンダーコントロール)。東京には、いかなる悪影響にしろ、これまで及ぼしたことはなく、今後とも、及ぼすことはありません」「汚染水の影響は、福島第一原発の0・3平方キロメートルの港湾内で、完全にブロックされています」 いずれも、とんでもない大ウソだ。それがばれるのに1日もあれば十分だったが、安倍総理は確信犯だった。総会で東京が選ばれるまでの間さえ、なんとかもてばよいと考えたのだろう。 福島事故を矮小化することで各国の不安感を取り除き、五輪を東京に持ってくることに成功したのだ。 あれから6年半。安倍総理は、再び、大ウソをつこうとしているのではないか。 聖火リレーが始まる3月26日、安倍総理は福島を含めた東日本大震災の被災地の復興について発言するだろう。その時果たして、安倍総理は、何と言うのか。 「福島(被災地)が見事に復興した姿を世界中の皆さんに見ていただけることは、私の最も大きな喜びであります」とでも言うつもりかもしれない。 さすがに、それには気が引けるだろうから、「完全な復興まであと一息のところにたどり着きました」と言うかもしれない。 「嘘つき東電」の廃炉計画でさえ、廃炉まであと30年。実際にはどれだけかかるかわからない。復興が「あと一息」と言っても、大ウソに変わりはない。 安倍総理にとって幸運なことに、新型コロナウイルス騒ぎのせいで、福島事故関連の報道は例年よりかなり減っている。仮に安倍総理が再び大ウソをついても、おそらくメディアではほとんど批判されずに終わるだろう。 世界を騙す大ウソをついた総理の責任を問わない私たち日本人。 再び世界への大ウソを許すとしたら、これは安倍総理の罪では済まない。こんな総理をあれから6年半も野放しにした私たち日本国民の罪が問われるのではないだろうか。
【出典】※週刊朝日 2020年3月27日号
|
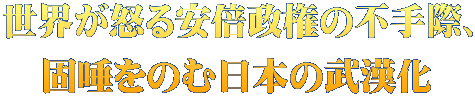 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
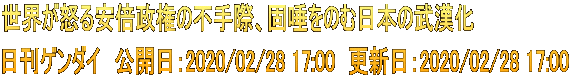 噂が出回った先月末には「デマ」だと完全否定したまさかの「東京五輪中止」が現実味を帯びてきて、橋本聖子五輪相らが火消しに躍起だ。 国際オリンピック委員会(IOC)の重鎮であるカナダのパウンド委員が、3カ月後の5月になっても日本で新型コロナウイルス感染が収束していなかったら「中止を検討するだろう」とAP通信に発言したことが波紋を広げている。 同委員は「開催可否の判断は5月下旬までに下される」と述べており、IOCのコーツ調整委員長も自身の地元である豪州メディアに27日、「5月判断」との認識を示した。 「私はマスクをしないで最後まで頑張ろうと思っている」――。東京五輪組織委員会トップの森喜朗会長が披露したこんな非科学的な根性論は、世界に通用しないということだろう。 27日、IOCのバッハ会長が緊急の電話会見に応じて「予定通り実施へ全力」と、とりあえずの沈静化を図ったが、中止論の背景に日本という国に対する“世界の不安”があるのは間違いない。 安倍政権の不手際で日本は武漢化した。世界はそう見ている。クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」で感染者が爆発的に増えたことで日本政府の対応に疑問を抱いた海外メディアは、下船時に陰性の乗客を公共交通機関で帰したことを知ってさらに批判を強め、「道連れにされたらかなわない」とばかりに酷評している。 米ブルームバーグ通信は「日本が急速にコロナウイルスの温床に」という見出しで、<日本は最も危険な場所の1つに浮上しており、安倍政権が感染拡大を阻止できなかったと批判されている>と報じた。 米紙ワシントン・ポストは<安倍政権はプレッシャーを感じるのが最も遅かった>と、他国の首脳と比較して皮肉り、<クルーズ船の新型コロナウイルス感染に関する日本の対応は『完全に不適切』だと衛生専門家が言明>と伝えた。 米紙ウォールストリート・ジャーナルは「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客だった医者の話を掲載。<私が感染していなかったことが驚きだ。ウイルスは野火のように船に広がった。日本政府は我々を感染させるために培養皿の中に閉じ込めたというのが私の推論だ>と証言したというから、愕然である。 「海外メディアが厳しい論調なのは、ひとえに自国民がクルーズ船に閉じ込められていたからでしょう。乗客乗員への扱いが本当に酷かったと受け止めている。加えて、厚生労働省がきちんと情報を出していないことにも不満が高まっている。国際感覚が分かっていないと思われています」(医療ガバナンス研究所理事長・上昌広氏) 英ロイター通信にまで「安倍首相はどこに行った」という記事を書かれたからか、安倍は政府の対策本部で今さらながらに前面に出て発言し始めた。 後手後手対応と責任回避の保身ばかりで、自治体や個人への“丸投げ”批判に耐えかねたのか、27日は、全小中高校に週明けの来月2日から春休みまでの臨時休校を呼びかけるという極めて異例の要請に踏み込んだ。 米CNBCテレビに登場した米食品医薬品局の前長官はこう言ったという。 「日本はコロナウイルスがパンデミック級に感染拡大するかを予測する上で、重要な指標になるだろう。我々は日本の状況を非常に注意深くウオッチする必要がある」 世界が固唾をのんで見守っている。
感染拡大が止まらず、国民もパンデミック目前を意識せざるを得ないからだろう。日本のあちこちで、パニック状態の混乱が発生している。 ワイドショーがこぞって取り上げた映像には仰天した。横浜のドラッグストア前で、マスクを求める列に割り込んだと取っ組み合いの喧嘩が起き、流血騒ぎとなったのだ。 政府が「増産態勢によりマスクの毎週1億枚供給が確保された」と言っても、店頭はいつも空っぽ。入荷するかどうかも分からないのに開店前に行列ができる。 コロナウイルスの有無を確認するPCR検査を受けたくても受けられない状態が続き、「政府は感染者数を少なく見せるために、検査させないようにしている」という疑心暗鬼が拡大。保健所の相談窓口への電話が鳴りやまない。 お隣の韓国は毎日数千件態勢で検査しているのに、日本では1日平均900件だと加藤厚労相が明かしている。なぜこうも違うのか。やっぱり日本はおかしい。国民の不安と不信は募るばかりだ。 花王や日本たばこ産業(JT)が27日、新たに全社員を対象にした在宅勤務の実施を発表したが、大手企業を中心としたテレワークの拡大は、政府に任せられないという究極の“自己防衛”でもある。 コロナ対策での政府の初動ミス、判断ミスは重い。そんな中での全国の小中高校への臨時休校の要請。一見「子供の健康と安全を考えた判断」と映るものの、1カ月もの長期にわたって子供が家にいたら共働き家庭はどうしたらいいのか。 安倍の発言はそうした具体的な事情や対策を検討したうえでのものなのか。日本中がますます大混乱である。 「政府がパニック状態に陥っているのですから国民もパニックになりますよ。全国の小中高校を休校にするのも、データに基づいて行っているのか。新型コロナの感染は高齢者や糖尿病などの持病のある人がより危険で、子供や若い人は重篤化もしにくいことが分かっています。『この1、2週間が感染拡大防止に極めて重要だ』という政府の見解も何か根拠があるのか。2月になって検査を始めたから、いま陽性になる感染者が増えているだけで、もっと以前から蔓延していたかもしれないのに。政府の対応のまずさが国民のパニックを招いているのです」(上昌広氏=前出) 日経平均は27日、2万2000円台を割り込んだ。新型コロナ禍関連倒産は、愛知の老舗旅館に続き、2例目が出た。コロッケ製造・販売やレストラン運営の北海道の会社だ。 いずれも中国からのインバウンド客の激減が直撃した形だが、問題は外国人だけじゃない。イベントの自粛ラッシュや市中感染不安の拡大で日本人も移動をしなくなる。「人・物・カネ」が流れなければ経済は停滞。その影響は計り知れない。 経済評論家の斎藤満氏が言う。 「コロナ懸念で先週21日に世界の株価が下落した際、通常なら『リスクオフ』で買われる安全資産の日本の円が売られる“珍事”が起きました。安倍政権のコロナ対応がお粗末過ぎて、金融市場の日本に対する見方はガラリと変わったのです。米国では経済番組のコメンテーターらが日本をウイルスの感染源という意味で『エピセンター』と呼んでいます。日本株の暴落も外国人が売りに走っているからです。インバウンドの縮小は当初は中国が原因でしたが、今は日本自体が原因になってきている。米国は日本への渡航警戒レベルを『2』の注意強化国に引き上げた。これからビジネスマンも日本に来られなくなり、経済へのダメージはさらに加速するでしょう」 自民・公明は新型コロナの追加経済対策として、来年度の補正予算案編成を政府に求める方針だ。 国会では来年度の当初予算案が審議中というのに、もう補正予算の話が出てくるバカげた状況は、安倍政権の経済無策を物語っている。恐慌目前になってから動いたって遅すぎる。 米紙ニューヨーク・タイムズが<壊滅的な台風と増税により、日本経済はすでに苦境に立たされている。そしてコロナウイルスが、日本を本格的な景気後退に陥れるおそれが出てきた>と書いていた。確かにいまの日本はその通りの惨状である。 【出典】日刊ゲンダイ 公開日:2020/02/28 17:00 更新日:2020/02/28 17:00
|
| 【出典】日刊ゲンダイ 公開日:2020/02/28 17:00 更新日:2020/02/28 17:00 |
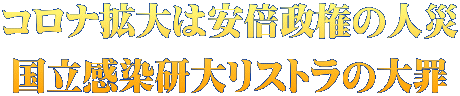 |
||||
|---|---|---|---|---|
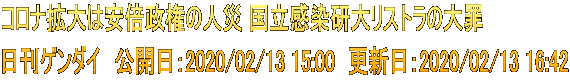 ようやく、安倍政権が重い腰を上げる。ついに4人が重症。新型コロナの感染が加速度的に広がる中、ウイルス検査の態勢強化など緊急対策に乗り出すが、しょせんは付け焼き刃の対応だ。これまで、感染症対策をおろそかにしてヒトやカネをバッサリ削ってきた“人災”のツケが回ってきた。 ◇ ◇ ◇ 現在、ウイルス検査や分析などの対応に追われているのは国立感染症研究所だ。米国では、感染症について「情報収集と発生時の対応」はCDC(疾病予防管理センター)、「研究・開発」はNIH(国立衛生研究所)、「ワクチンの品質評価」はFDA(食品医薬品局)と、3つの機関が分業している。 この3つの役割を感染研は一手に担っている。 近年、インフルエンザ、麻疹、風疹、梅毒などの流行が見られ、感染症の脅威は高まっている。しかし、感染研はすさまじい大リストラを食らってきた。 2009年度に61億円あった研究費と経費の合計額は、18年度はなんと41億円。3分の1に当たる20億円も減らされてしまった。研究者も09年の322人から、現在は307人。組織はスカスカにされている。 理由は十把一絡げの国家公務員の削減だ。山野美容芸術短大客員教授の中原英臣氏(感染症学)が言う。 「感染研が担う役割や仕事量からして、300人余の研究者は極めて少人数です。10年間でさらに人も金も減らしているのは、安倍政権が感染症対策を軽視している表れといえます」
<人員や経費が削減される中、研究所の業務や研究の範囲は拡大し続けており、個々の職員の努力に依存した運営には限界がきている><予算・人員の裏付けをつけることが重要であり、研究所は、その国民に対する使命の質と大きさに鑑み、「国家公務員削減計画」からの除外対象とすべきである> 悲鳴のような報告書が出されても、安倍政権は、予算・人員を削り続けた。 さらに昨年4月9日、共産党の田村智子参院議員が内閣委員会で、感染研のリストラ問題を取り上げた。政府は「(感染研は)重要な機能を有していることは認識しています。新規増員を措置してきている」(宮腰光寛内閣府特命相=当時)と答弁。 感染研によれば、「国会で予算が通れば、新年度は1人増えて、308人になります」(総務課)という。増員幅はスズメの涙だ。 安倍政権が評価委や田村議員の指摘に耳を傾けていれば、新型コロナウイルスはここまで感染が拡大しなかったのではないか。 「予算、人員削減のツケが回ってきました。例えば、クルーズ船の約3700人全員のウイルス検査は、マンパワー不足の問題で決断が遅れました。感染が確認された検疫官が防護服を着ていなかったのは、金がない証拠です。安倍首相のいう国防は、高額の軍艦や飛行機を買うことですが、感染症から国民の命を守ることの方が大事な『国防』です」(中原英臣氏) 安倍政権は新年度予算案に過去最高となる防衛費5・3兆円を盛り込んだ。 政権発足後、8年連続アップで、6000億円も増やしている。いくらかでも感染症対策に回したらどうだ。 【出典】日刊ゲンダイ 公開日:2020/02/13 15:00 更新日:2020/02/13 16:42 |
| 【出典】日刊ゲンダイ 公開日:2020/02/13 15:00 更新日:2020/02/13 16:42 |
 昨日おこなった施政方針演説で、やたら「夢」だの「希望」だのといったフレーズを連発し、ことごとくオリンピックの話題を政策とつなげた安倍首相。これには当然ながら「東京五輪の政治利用だ」という声があがっているが、よりにもよって施政方針演説で中身がスカスカの政策を五輪の話題でごまかすなどというのは、安倍政権の無能っぷりを象徴するかのようだ。 この五輪の政治利用にかんしては別稿でお伝えするのでそれをお待ちいただきたいが、じつは昨日の施政方針演説をめぐって、信じられないような事実があきらかになった。 安倍首相は施政方針演説のなかで地方創生について言及し、ある男性の実名を出しながら、Iターンの事例を紹介した。だが、それがフェイクまがいだったというのだ。 いったい安倍首相は何と語っていたのか。まずは該当部分のスピーチを引用しよう。 「東京から鉄道で7時間。島根県江津市は『東京から一番遠い町』とも呼ばれています。20年以上、転出超過がつづき、人口の1割に当たる2800人が減少した町です。 しかし、若者の起業を積極的に促した結果、ついに一昨年、転入が転出を上回り、人口の社会増が実現しました。 ◯◯◯◯さんはパクチー栽培をおこなうため、東京から移住してきました。農地を借りる交渉をおこなったのは、市役所です。地方創生交付金を活用し、起業資金の支援を受けました。農業のやり方は地元の農家、販路開拓は地元の企業が手助けしてくれたそうです。 『地域みんなで、手伝ってくれました』 地域ぐるみで若者のチャレンジを後押しする環境が、◯◯さんの移住の決め手となりました。 『地方にこそ、チャンスがある』。そう考え、地方に飛び込む若者を、力強く応援してまいります」(注:伏せ字の部分は演説では実名) 普通に演説を聞けば、この移住した男性の話は現在進行形のように思える。だが、中国新聞デジタルが昨晩、こう銘打って記事を配信したのだ。 「安倍首相の施政方針演説の起業支援で紹介の男性、既に島根県江津市から転居していた」 この記事によると、中国新聞の取材ではこの男性は〈昨年末に県外へ転居〉しており、さらに〈昨年末にこの会社を辞め、既に江津を離れていた。個人的な事情という〉と伝えているのだ。 言っておくが、施政方針演説というのは政府のこれからの1年の基本方針を示すためにおこなわれる重要なものだ。そして安倍首相は、この男性のエピソードを地方創生の企業支援政策の“成功例”として紹介した。それが〈個人的な事情〉とはいえ、すでに会社を辞めて土地も離れていたのだ。この男性個人の選択や理由はどうあれ、地方支援の政策の成功例として持ち出すのは、どう考えても不適切だろう。しかも、男性が辞めたことに一切触れないで、『地方にこそ、チャンスがある』などといった政策宣伝につなげるのは、フェイクとしか言いようがない。 それにしても、安倍首相はなぜこの男性の話を実名で持ち出したのか。中国新聞の記事では、市は〈首相が演説で示した市の人口増減のデータなどに関する国からの問い合わせには昨年末に回答していた〉というが、〈男性のことが演説に盛り込まれているとは知らなかった〉という。 施政方針演説というメディアも大々的に伝えるスピーチだというのに、安倍官邸は事実関係を調べていなかったのだろうか。演説では引用したとおり、安倍首相は実名を挙げただけではなく、男性の「地域みんなで、手伝ってくれました」というコメントまで紹介していた。しかし、もし、実名を挙げた男性に安倍官邸側が直接取材したのなら、普通は退社や県外に移った事実を知らされるはずで、こんな紹介の仕方にはなっていないだろう。 ということは、コンタクトはとっており事実関係も知らされていたが、それを無視してスピーチに使用したか、あるいは安倍官邸側は男性に取材もせず、過去にメディアで取り上げられた二次情報をもとにスピーチをつくった。そういうことではないか。 当たり前だが、どんなかたちであれ、この男性には何の非もない。しかし、もし安倍官邸側が事実を知りながら無視したり、そもそも取材もしていないとなれば、これは大問題だ。 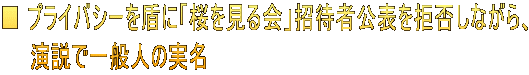 こんなありえないことが起きてしまうのが、安倍政権の怖さなのだ。実際、安倍首相には、スピーチや国会答弁で虚偽・フェイクまがいの話を喧伝してきた“前科”がある。 たとえば、安倍首相が9条に自衛隊明記する改憲の理由としてしきりに持ち出していた、「自衛官が息子に『お父さんは違憲なの?』と目に涙を浮かべながら言われた」というエピソードがそうだ。安倍首相はことあるごとにこのエピソードを取り上げ、「自衛隊の幹部から聞いた」「ある自衛官から聞いた」と語ってきた。 しかし、国会で小中学校と自衛隊駐屯地のそばで育ったという立憲民主党の本多平直衆院議員が「こんな話が出たことがない」と質疑のなかで述べると、安倍首相は血相を変えて「私が嘘を言うわけないじゃないですか!」と喚き立て、「資料を出せと言うんであれば出させていただく」と大見得を切った。 ところが、その後の衆院予算委員会で、安倍首相は出すと言っていた資料も出さず、「防衛省担当の総理秘書官を通じて、航空自衛隊の幹部自衛官から伺った話」と答弁。つまり、「自衛隊の幹部から聞いた」「ある自衛官から聞いた」と語ってきたのに、実際には又聞きだったことがわかったのだ。 しかも、本サイトが調べたところ、「お父さん違憲なの?」のネタ元だと思われる元自衛官の話が「正論」(産経新聞社)に掲載された2017年6月と同時期に、同じような話が極右界隈で語られはじめていた。ちなみに安倍首相が9条に自衛隊を明記する改憲案をぶちあげたのは同年5月。ようするに、改憲案を正当化するために、改憲勢力や自衛隊出身の右派論客などが古いエピソードを持ち出した疑いがあるのだ(過去記事参照)。 雑誌などで語られていたような話を「自分が直接聞いた話」だと嘘をついて国会答弁やスピーチで平気で繰り返し、改憲の道具に使う──。大前提として、「お前の父ちゃん憲法違反!」などといじめられた子どもがほんとうにいるのだとしたら、おこなうべきはいじめの解消・解決。そのエピソードを持ち出して改憲の理由にすること自体がどうかしているのだが、ともかく、これが安倍首相の常套手段なのだ。しかも、そのやり口はスピーチライターを含む側近たちに完全に広がり、官邸全体の方法論と化している。 こうした状況を踏まえると、今回の施政方針演説の問題もさもありなんと言わざるを得ないが、今回の演説でもうひとつ指摘しておきたいのは、安倍首相の「個人情報」の考え方だ。 安倍首相は「桜を見る会」問題では、招待者について「個人に関する情報」だと言い張ってすべての回答を拒否している。それは自ら招待されたことを宣伝材料にしていたジャパンライフ会長の件についても同じで、当人が招待されたとあきらかにしているにもかかわらず、安倍首相はやはり「個人に関する情報なので回答は差し控える」の一点張りだ。 事ほどさように「個人情報」の保護遵守を言い募るのに、一方では国会の演説でカジュアルに一般人の実名を挙げて、結果このような騒ぎを巻き起こす……。結局、安倍首相の言う「個人情報」に対する認識とはこの程度のもので、都合が悪いときの隠れ蓑でしかないのだ。 威勢のいい言葉や美辞麗句を並べ立て、中身が空っぽだっただけではなく、地方創生の成功例として語った話が実際にはフェイクまがいだったというこの疑惑。安倍首相に説明が求められることは言うまでもない。 (編集部) 【出典】LITERA 2020.01.21 05:30 |
|---|
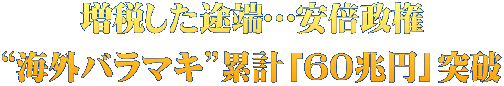 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
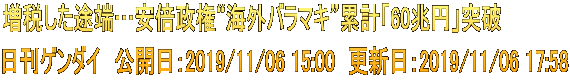 「国民目線」からはほど遠い決断だ。10月の消費増税は「税と社会保障の一体改革」の名の下に、税収を社会保障の安定財源に充てる名目にしていたが、直近で安倍首相が決めたのは、東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国への「出資倍増」だった。庶民に痛みを強いる消費増税実施直後のタイミングでの“海外バラマキ”に批判の声が続出するのは時間の問題だ。 ◇ ◇ ◇ ASEAN首脳会議でタイを訪れていた安倍首相は日本時間の4日夜、外務省所管の国際協力機構(JICA)への出資を今後倍増させ、ASEAN諸国のインフラ開発などを支援していく方針を表明。この発言に対し、SNSなどでは〈また、外国にばら撒きかよ〉〈諸外国に出す金があるなら、(消費税を)増税するなよ〉〈途上国の外国人よりも、氷河期の日本人を支援すべき〉といった批判の声が相次いだ。 そりゃあそうだろう。第2次政権が発足した2012年以降、安倍政権は海外諸国にドヤ顔でカネをばらまき続けているからだ。 昨年1月26日の参院本会議の代表質問で、社民党の福島瑞穂議員は〈総理が表明した(海外への支援)額を機械的に加算した場合、円借款や一部重複部分を含め54兆3621億円になるという回答が(外務省から)あった〉と指摘。〈社会保障を削って、なぜこの大盤振る舞いなのですか〉と追及すると、安倍首相は〈54兆3621億円は、民間資金と重複計算により額が膨大に膨らんでおり、極めて誤解を招く数字〉とムキになって反論。〈(本来の総額は)2兆8500億円〉とか言っていたが、その詳細な内訳はいまだに分からずじまいだ。 このやりとり以降も、安倍政権は平然と“海外バラマキ”を継続。18年4月、過激派組織「イスラム国」との戦闘終結後のイラク復興支援名目で、同国の上水道整備などのために約350億円の円借款供与を決定したほか、同年10月には、インドの高速鉄道計画などに3000億円強、さらに今年4月にはパナマ首都圏のモノレール建設事業を巡り、約2810億円の円借款を決めた。そして5月末は、バングラデシュの鉄道や商業港建設に関連し、1300億円規模の円借款を約束するなど、ざっと取り上げた大型案件だけでも、バラマキ金額は約7500億円にも上る。総額でいえば、ざっと55兆円を突破している計算だ。 さらに言えば、昨年末に閣議決定した19~23年度「中期防衛力整備計画」に基づくステルス戦闘機の“爆買い”だって、トランプ大統領の要求に屈した安倍首相の米国への巨額な“バラマキ”に等しい。1機116億円とされる戦闘機を147機購入する計画で、維持費を含めると日本の支出額は約6兆2000億円。つまり、バラマキ総額は実に60兆円を超えているのだ。 「海外支援に資金を支出することは重要なことかもしれません。しかし、政府はこれまで多額の出資をし、どれだけの成果を上げてきたのかが全く見えない。安倍首相は、大枚をはたいて各国首脳を味方につけたかのような気分に浸っているだけではないか。給料が上がらない中、消費増税に苦しむ国民が多いのに、海外へのバラマキに税を費やしている場合ではないはずです」(経済ジャーナリスト・荻原博子氏) 消費増税した途端に海外にカネをばらまき始めるというのは、もはや、宰相としても政治家としても、マトモな頭じゃない。これじゃあ、いくら増税してもキリがないだろう。「カップ麺が1個400円」などと国会答弁で平気で言ってのけるバカ者だらけの政権にこれ以上、税金を使わせたら国が滅ぶ。 【出典】日刊ゲンダイ 公開日:2019/11/06 15:00 更新日:2019/11/06 17:58
|
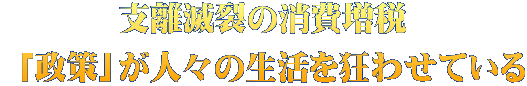 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
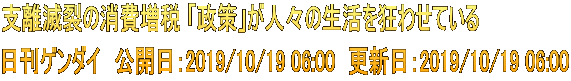 消費税2ケタ時代が始まり、つくづく思ったのは、責任感や国民への奉仕の精神を持たない人たちが政策を担当すると、おかしなものが出来上がってしまうということです。 消費税は本来、財政再建のために導入され、順次、税率が引き上げられるのも財政健全化のためだったはずです。 しかし今や、安倍政権は自分たちのやりたいことのために増税している。突然、持ち出してきたのが、「幼児教育・保育の無償化」です。 今回の増税分の半分を、このいかにも子育て世代向けの“点数稼ぎ”くさい政策に充てることになってしまいました。 しかも、当事者たちが本当に欲しい制度ではないから、実は点数稼ぎにさえなっていない。支離滅裂です。 さらには、増税による消費落ち込み対策として、ポイント還元を導入し、ついでにキャッシュレス化も推進してしまえ、みたいな、訳の分からないことも起きている。 世のため、人のため、という本気の問題意識が欠如しているので、増税効果を自ら相殺するようなことになってしまうのです。 食品を軽減税率にして8%に据え置いたのも、一体、誰のための政策なのか。突き詰めて検討されたわけではないでしょう。「軽減税率なら食品」と短絡的に決めただろうにおいがプンプンする。食品は多様で、高額なものもあり、購入者は金持ちだったりする。逆進性の排除には全く役に立たない可能性があります。 そう考えると、消費増税直前の9月末に、トイレットペーパーをいくつも買い込むという消費行動に追い込まれた私たちは、本当に哀れだと思います。無責任な政策が人々を不自然な行動に追い込んでいく。 本来、政策は、不自然なことやつじつまの合わないことを修正し、自然でバランスの取れた状態に戻すために存在している。経済・社会に対する「外付け装置」として均衡の保持と回復に努める。それが政策の役割です。 ところが、そういう役割のはずの政策が、逆に人々の生活を狂わせているのが現状。これは酷く恐ろしいことです。 コトは消費増税の問題に限りません。金融政策の失敗もそうです。直近では、関西電力の金品受領という驚くべき事案も明らかになりました。これも日本の原子力政策の怪しい体制に絡んで噴出した問題だといっていいでしょう。 そして、もうひとつ。老後に2000万円不足するという問題です。政府の意図するところではないと金融庁の報告書は撤回されましたが、「貯蓄から投資へ」という方針は、人々を危ない橋へ追いやる間違った政策です。 普通の人たちは、健全な貯蓄によって生活を維持できることを望んでいる。それが可能な状況をつくっていくことが、本来の政策の役割のはずです。 政策が人々の生活をよりよくするものになっていない。むしろ私たちは政策の餌食になってしまっている。 ロクでもない政策とその背後にある安倍政権の下心から、日本の経済・社会を救出しなければいけない状況になってきました。 「日本経済救出大作戦」に踏み切る必要が出てきたと思います。 【出典】日刊ゲンダイ 公開日:2019/10/19 06:00 更新日:2019/10/19 06:00
|
| 【出典】日刊ゲンダイ 公開日:2019/10/19 06:00 更新日:2019/10/19 06:00 |
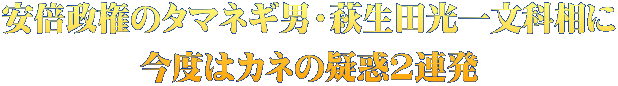 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
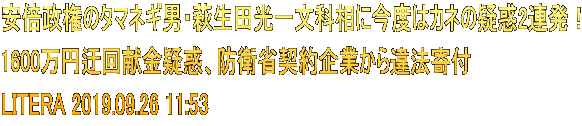 安倍内閣からまたも疑惑が飛び出した。安倍首相の側近中の側近で、先日の内閣改造で初入閣を果たした萩生田光一文科相に公選法違反疑惑が持ち上がったのだ。 この問題を報道したのは、23日付のしんぶん赤旗。記事によると、2017年10月におこなわれた総選挙の期間中、萩生田氏が代表を務める政党支部「自由民主党東京都第二十四選挙区支部」は約1847万円もの企業・団体献金を集めていた。 一方で同支部は、衆院が解散した9月28日から11月10日のあいだに計6回、「はぎうだ光一選挙対策本部」に総額1600万円を寄付していたという。 政治資金規正法では、癒着や汚職を防ぐために公職の候補者の後援会などへの企業・団体献金は禁止されている。そのため、政党支部を迂回させて、本来は受け取ることのできない企業献金を得ていたのではないかとみられる。 実際、以前に萩生田氏を支援する団体で役員を務めていた空調機器販売会社の会長は、しんぶん赤旗の取材に対し、企業名で総選挙の公示直後に100万円を献金したことについて証言。 「覚えていますよ。正式な手続きをして出させてもらいました」と答え、 〈萩生田氏個人への選挙応援のための献金だった〉ことも認めたという。 だが、萩生田氏の選挙運動費用収支報告書では、収入として「自由民主党東京都第二十四選挙区支部」からの1600万円しか記載していない。 この点について、上脇博之・神戸学院大学教授は「本来は候補者個人に対して行われた企業・団体献金を、政党支部への献金として政治資金収支報告書に記載したことになり、政治資金規正法上の虚偽記載罪の疑いが生じます」と指摘。 また、公選法では選挙運動に関するすべての収入と支出を報告するようを定めており、公選法違反の虚偽記載に当たる可能性もあるのだ。
しかも、先日本サイトでもお伝えしたように、今回の内閣改造で大臣に返り咲いた高市早苗総務相をめぐっても、公選法違反疑惑が取り沙汰されている。 この問題は、やはり2017年におこなわれた衆院選の選挙期間中に、高市氏が代表を務める自民党奈良県第2選挙区支部が、当時、警察庁や防衛省と取引のあった奈良市の寝具リース会社から30万円の献金を受けていた。 公選法では、国と契約を結ぶ企業などから国政選挙に関連して献金を受けることを禁止しており、あきらかに公選法違反にあたるだろう。 この問題を報じた共同通信が18日付記事では、取材に対して高市総務相の事務所は「企業と国との契約の有無を知りうる方法はないが、指摘の通りなら結果的に公選法に抵触する恐れがある」と、公選法に抵触する可能性を指摘していた。 ところが、翌19日におこなわれた会見で高市総務相は、国との契約を知らなかったという理由で「公職選挙法への抵触はまったくない」と主張。 「選挙制度や政治資金を所管する大臣として、疑義を指摘されるのは不本意なので道義的観点から返金した」と述べたのだ。 「疑義を指摘されるのは不本意」って、何を寝ぼけたことを言っているのか。 「知らなかったからセーフ」が通用するなら法律の意味などないし、所管大臣がこんな態度ならなんでも「知らなかった」で済まされてしまうことになる。はっきり言って言語道断だ。  しかも、萩生田文科相にも高市総務相とまったく同じ疑惑が浮上。同様に2017年の総選挙期間中に防衛省と取引のあった企業から100万円の寄付を受けていたと22日付の読売新聞が報道。 だが、萩生田文科相の事務所も「(国発注の)事業をしていたとは知らなかった」と言い訳した。 その上、安倍首相の側近である萩生田氏と高市氏に持ち上がったこれらの疑惑について、テレビも新聞も追及の動きはまったくなし。 ワイドショーではあいも変わらず韓国のチョ・グク法相の疑惑を熱心に追及しているのに、である。 いや、そもそも萩生田氏と高市氏が大臣に登用された段階から、「こんな組閣が許されるのか」と批判が巻き起こっていない時点でおかしいのだ。
それをよりにもよって安倍首相は文科省の大臣に抜擢したのである。 さらに、高市氏は総務相だった2016年に“国は放送局に対して電波停止できる”と国会答弁し大問題に。 当時、池上彰氏も〈まるで中国政府がやるようなことを平然と言ってのける大臣がいる。驚くべきことです。 欧米の民主主義国なら、政権がひっくり返ってしまいかねない発言です〉(朝日新聞2016年2月26日付)と指摘していたが、やはり安倍首相は露骨な言論封殺を示唆した高市氏を総務大臣に再び登用したのだ。 しかし、こんなあからさまな人事がおこなわれたというのに、テレビは小泉進次郎氏の初入閣を大きく取り上げるばかりで、萩生田氏と高市氏をはじめとする新大臣の過去の問題や疑惑をスルーした。 しかも、萩生田文科相は就任記者会見で加計学園問題の関与と安倍首相からの指示を否定した上、「私としては私の発言していないことが私の発言だといって文書で出てきて、大変疑念をかけられ、迷惑した」などと文科省を非難。 高市総務相も「過去に電波を止めるといった発言をしたことはない」と開き直っている。普通に考えて、国民を舐めきっているとしか言いようがないが、これらの暴言も、テレビはまったく取り上げようとしないのだ。 国民をバカにした人事と、人を食ったような発言しかしない大臣。 しかし、こうした実態も浮上した疑惑も伝えられることなく、なかったことになってゆく──。 何度、ひっくり返っていてもおかしくはない安倍政権がひっくり返らないのは、ひとえにメディアのアシストによるものだと痛感せずにはいられない。 (編集部) 【出典】LITERA 2019.09.26 11:53
|
| 【出典】LITERA 2019.09.26 11:53 |
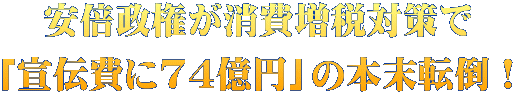 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
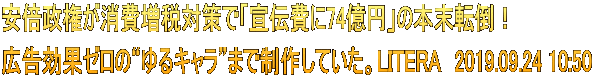 10月1日からいよいよ消費税の10%への増税が実施される。貧富の格差がどんどん激しくなっている中で、逆進性の高い消費増税を導入することは庶民の生活をさらに圧迫するのはもちろん、経済状況を取り返しがつかないくらい悪化させることが、専門家の間でも指摘されている。 だが、国民の怒りの声はあまり大きくなっておらず、安倍政権の詐術に騙されてしまったのか「少子高齢化が進む中、社会保障の充実のためにはしようがない」という声がかなりの部分を占めている。 しかし、この事実を知ってもまだ「増税はしようがない」と言っていられるだろうか。安倍政権は今回の消費増税にかこつけ、なんと消費税対策の「広報・宣伝」に74億円もの巨額の税金を投入、その中には、なんの宣伝効果もないゆるキャラ制作代まで含まれていたというのだ。 安倍政権は「社会保障の充実」を名目に10%への引き上げを行うのだが、実は約5.6兆の税収増見込みのうち社会保障の充実にあてられるのは約1.1兆円。 その一方で、2兆円を超える金を増税による消費落ち込みを防ぐ「景気対策」としてバラマくことになっている。具体的には、最大2.5万円分の商品券を2万円で購入できると謳う「プレミアム付商品券」制度や、クレジットカードなどキャッシュレスでの買い物の際、特定の条件において最大5%のポイントを還元する制度(以下、ポイント還元制度)などが実施される。 消費増税のお題目である「社会保障の充実」に充てる金よりも「景気対策」でバラまく金が倍近く多いということ自体、信じられないが、さらに、この「プレミアム付商品券」制度と「ポイント還元制度」のための宣伝・広報費として、74億円の予算がつけられているというのだ。 しかも、ひどいのはその中身だ。たとえば、内閣府が担当する「プレミアム付商品券」の特設ホームページを覗いてみるといい。いきなり虫眼鏡を手に持つ招き猫風の「ゆるキャラ」のイラストが目に飛び込んでくる。名前を「確にゃん」というらしい。 「あなたは対象者? 確認したら申請にゃん!」なんて喋っている“確にゃん”だが、内閣府はこうした広報になんと「14億円」もの予算を組んでいるらしいのだ。 ゆるキャラを使った行政の広報については、財務省が2014年の予算執行調査で独立行政法人に対して、目標がないままマスコットキャラクターを多用し、効果が上がらないまま無駄な予算を使っていることを指摘している。 ところが、今回、首相のお膝元である内閣府がよりにもよって消費税対策でその“無駄遣い”を大々的に行っていたというわけだ。 いったい安倍政権は何を考えているのか。内閣府に電話取材すると、プレミアム商品券の担当者は「宣伝費の予算上限が14億円」であることを認めたうえで、このように説明した。 「宣伝費は、チラシやポスター等のほか、テレビやラジオなどのマス系のメディアあるいはインターネットを通じた“広報のパッケージ”で予算を組んでいます。ですので、『ゆるキャラ制作費』みたいなものは存在しません。よく誤解されるのですが、“確にゃんを制作するためにいくらつぎ込んだ”というような世界ではなくて、基本的な広報戦略における統一コンセプトのもと、デザインのひとつとして、こうした親しみやすい猫のキャラクターを使っていこうということになりました」 内閣府担当者によれば、プレミアム商品券の広告宣伝は、公募で決定した事業者に包括委託したものだという。つまり広告代理店への外注だ。実際、官報などによると「プレミアム付商品券事業に係るクロスメディア広報業務」との名称で公募が行われ、今年の4月19日に大手の博報堂が落札していた。 安倍政権はプレミアム付商品券事業に1723億円の予算(2019年度)を計上しているが、少なくともそのうち14億円は広告代理店の懐に入ってしまうということらしい。 しかも、その巨額の税金をつぎ込んだ宣伝は効果を発揮しているのか。内閣府担当者はゆるキャラを使ったことについて、「プレミアム商品券は対象の方が限定されておりますので、事前に申請等をしていただかなければなりません。 まずは日常生活のいろいろな場面で目につきやすく、なおかつ“なんだろうこの猫は?”と、なんとなしに見ていたら“申請が必要なんだな”というふうに気づいていただくことが非常に重要でして」などと説明していたが、“確にゃん”を発表してからすでに数カ月が経ったが、このキャラクターのことを知っている国民はほとんどいないだろう。 こうした広報・宣伝費の巨額無駄遣いは経産省が担当する「ポイント還元制度」でも同様だ。こちらはなんと、宣伝広告費として60億円余りが注ぎ込まれるのだという。 本サイトは、経産省へも電話で数回にわたって取材を申し込んだが、同省キャッシュレス推進室は担当者の不在や多忙を理由に取材に応じなかった。 しかし、経産省がいくらごまかそうとしても、省のトップがこの巨額宣伝費投入の事実を認めていた。 今年2月、当時の経産相・世耕弘成がテレビ朝日の報道にいちゃもんをつける流れの中で、つい、こうつぶやいてしまっていたのだ。 〈一般的な「広報宣伝費」であるポスター・チラシの配布、WEBや新聞、テレビを通じた広報、説明会の開催等にかかる予算としては、消費者向け、中小・小規模事業者向け合わせて、60億円強を計上しています。〉 世耕大臣は自慢げに語っているが、ポスター・チラシの配布に、広告、説明会の開催で60億円なんてどうかしているとしか思えない。 いずれにしても、事実関係ははっきりしたはずだ。内閣府14億円+経産省60億円。社会保障の充実を謳って消費税を増税しながら、安倍政権は本当に計74億円もの金を宣伝費に使っているのだ。 この事実を知ると、安倍政権はもしかしたら、社会保障の充実どころか、景気維持すらまともに考えていないのではないか。そんな気さえしてくる。 実際、74億円を使って宣伝するプレミアム付き商品券もポイント還元制度も、その制度自体に様々な問題点が指摘されている。 たとえば内閣府はHPで、プレミアム付商品券を〈25%もお得に買い物ができる〉と謳っているが、これは“ひとりあたり最大2万5000円分の商品券を2万円で購入できる”という仕組みだ。 対象は住民税非課税の人と「学齢3歳未満の小さな乳幼児のいる子育て世帯」で、後者は3歳未満の子どものひとりにつき一枚、誕生日を一日でも過ぎていれば(2016年4月1日以前に生まれた子ども=引き上げ時に3歳半以上)対象にならない。 有効期限も税率引き上げ後から6カ月に限定されている。言うまでもなく2%の増税はずっと家計を直撃し続けるわけで、これでは「一時しのぎ」との批判が出ても仕方がないだろう。 プレミアム商品券は2015年にも消費税率8%引き上げに対する「緊急経済対策」として実施されたが、内閣府の分析ですらその経済効果は予算額2500億円の半分以下(1019億円)、みずほ総合研究所は個人消費の押し上げ効果を640億円程度と発表していた。 ポイント還元についてはさらに問題が山積している。これは、クレジットカードや電子マネーを使って「中小店舗」で買い物をしたとき、最大5%分のポイントがつくというものだ。期間は引き上げ時から9カ月。 そもそも制度自体が複雑であるというのはもちろん、キャッシュレス決済でのポイント還元は当然、高い買い物のほうが得られるポイントが多くなる。低所得者はカードの上限額が低かったり、そもそもそんな高額の買い物をする余裕などない。 消費税は逆進性があり、増税の負担は低所得者ほど重いのだが、ポイント還元制度も同じように「金持ち優遇」なのである。これでは、景気対策につながるわけがない。 要するに、安倍政権が景気対策として打ち出した制度は、いずれも金がかかるだけで、ほとんど効果が望めないものばかりなのだ。 しかも、これまで指摘してきたように、予算の全額が景気対策に使われるわけでもなく、かなりの金額が広告代店を儲けさせるだけの宣伝・広報費に投入される。 いや、広告費だけではない。ポイント還元制度では、2019年度予算2798億円のうち国民に還元されるのは1600億円程度で、残りは経産省などが経費として使う予定なのだ。この異常な予算配分に、政府内からは、首相に近い経産省が自分たちの利権拡大のためにポイント還元制度を強行したのではないかという声まで聞こえてきている。 何度でも言うが、本来、消費税率引き上げによる税収は「すべて社会保障の充実に使う」はずだった。 だからこそ、国民は生活がさらに苦しくなるのを我慢して、渋々消費増税を認めたのだ。にもかかわらず、安倍政権は、その貴重な血税を無駄遣いし、特定の省庁の利権拡大や企業を儲けさせるために使おうとしているのだ。 本当にこんなことを許していいのか。ここで怒らなければ、国民は安倍政権の奴隷かのように舐められ続けることになるだろう。 (編集部) 【出典】LITERA 2019.09.24 10:50
|
| 【出典】LITERA 2019.09.24 10:50 |
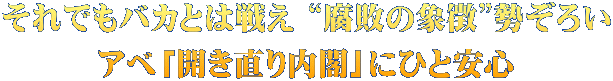 |
||||
|---|---|---|---|---|
 第4次安倍再改造内閣、どうなることかと不安だったが、まずは安心した。 安倍がまともな人材を集めて組閣していたら目も当てられなかった。 次の衆院選に向けて、国民の怒りも高まり、野党共闘の流れが出てきたのに、水を差されることになってしまう。 しかし杞憂に終わったようだ。19人の閣僚のうち17人が交代、13人が初入閣にもかかわらず、なんの代わり映えもしないのは、安倍政権の腐敗の象徴が勢ぞろいしたからだろう。 加計学園事件のキーパーソンで加計学園が運営する千葉科学大客員教授の萩生田光一を文部科学相にしたり、自身のウェブサイトが数カ月にわたり閲覧できなくなっている理由について「よくわからない」と答える78歳のおじいちゃんを科学技術・IT担当相にしたり、ネトウヨ路線に活路を見いだし、いつ暴発するかわからない河野太郎を防衛大臣にしたり、完全にカオス状態。衛藤晟一、加藤勝信ら、安倍友もしっかり入閣。 雲隠れしていた甘利明は党税制調査会長にもぐりこんだ。なお安倍は「総理大臣になるには、どうしたらいいのですか?」という小学生の質問に「友達をたくさん作ること」と答えてる。 一方で「外の目も入れていかなければ客観的な評価はできません」「今回の問題でなぜ近畿財務局の職員が自ら命を絶たなきゃいけなかったんですか」と公文書改ざん等を批判した石破茂および石破派は閣僚メンバーから完全にパージされている。わかりやすすぎる。 誰もが笑ったのが小泉進次郎の環境相就任だろう。私がツイッターで〈以前、進次郎さんの発言をほぼすべて確認したのですが、批判する場所が一か所もなかった。内容がゼロだから批判しようがない。「砂糖は甘いんです。僕は昔からそう思っている」みたいなことを遠くを見つめながら言う。 政治家にはあまり向いていないと思います〉と書いたら5日間で150万件を超えるインプレッションがあった。 要するに多くの国民が呆れ果てているということだ。揚げ句の果てには内閣府政務官に今井絵理子を起用。この人、不倫以外になにかやったのか。しかも1期目。安倍は「安定と挑戦」と言っていたが、これはわれわれ日本人に対する挑戦だろう。 役者は揃った。安倍政権はこれまでの路線を踏襲し、ぶれずに衆院選に突入してほしい。 (適菜収作家)
|
| 【出典】日刊ゲンダイ 公開日:2019/09/21 06:00 更新日:2019/09/21 06:00 |
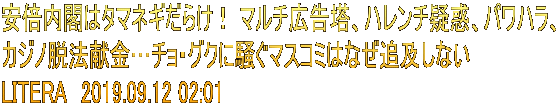 「新しい時代の国づくりを力強く進めていくための布陣を整えた」──昨日、第4次安倍第2次改造内閣が発足し、記者会見で安倍首相は新内閣について「自民党は『老荘青』、人材の宝庫です」などと語った。 「人材の宝庫」って……(苦笑)。この新内閣の実態は、どう見ても「お友だちの不良品一掃内閣」「極右不正政治家集結内閣」だろう。 とにかくひどい顔ぶれだが、これを見てまず思い出したのが、最近のワイドショーの報道だ。ワイドショーは、連日、文在寅大統領側近のチョ・グク氏のスキャンダルを取り上げ、法相就任を「日本ではありえない」「異常」などと攻撃してきた。 実際、9日放送の『情報ライブ ミヤネ屋』(読売テレビ)では、司会の宮根誠司がこんなことを言い放っていた。 「これ普通、日本だと“疑い”ですよ。家族でもなんでも、なにか“疑い”。怪しいことがあったら、まあ高岡さん(読売テレビ解説副委員長)、日本だったら総理大臣が任命しませんよね、法務大臣に」 「安倍総理だったら疑惑がある人を大臣なんかに任命しない」って、まったくよく言ったものだ。 『ミヤネ屋』をはじめとするワイドショーは、チョ・グク氏が玉ねぎのように皮を剥いても剥いても疑惑が噴出することから名付けられた「タマネギ男」という呼称を嬉々として連発してきたが、はっきり言って、安倍首相によるこの新内閣のほうがずっと「疑惑のある人」だらけの「タマネギ内閣」だろう。 まず、国民を舐めきっているとしか思えないのが、再入閣組だ。高市早苗氏は総務相に再任したが、高市氏は総務相だった2016年に“国は放送局に対して電波停止できる”と国会答弁し、大問題に。 また、厚労相に返り咲いた加藤勝信氏も、昨年、働き方改革一括法案の国会審議でデータ捏造が発覚した上、インチキ答弁を繰り返したばかりだ。 この高市総務相の暴言と加藤厚労相のデータ捏造とインチキ答弁は、その段階で大臣を辞任すべき問題だった。だが、安倍首相は側近である両大臣の問題をスルーして続投させ、内閣改造で首を挿げ替えただけ。 その結果、こうして問題大臣が同じポストに再び収まったのだ。信じられない人事と言うほかない。 しかも、この2人には重大な疑惑とスキャンダルもある。高市氏はやはり総務相だった2016年に計925万円の「闇ガネ」疑惑が浮上するなど、カネにまつわる疑惑が数々持ち上がってきた(詳しくは過去記事参照)。 さらに、加藤氏は、マルチ商法としてたびたび社会問題化し、昨年経営破綻したジャパンライフの“広告塔”を務めてきた人物。ジャパンライフは史上最大の消費者被害を出した安愚楽牧場に次ぐ被害規模として現在、捜査が進められているが、そんななかで“広告塔”としての責任を問うことなく大臣に再任するなど、まったくもってありえない。 だが、これはまだ序の口。安倍内閣過去最多の13名となった初入閣組も、かなりの「タマネギ」揃いだ。 そのひとりが、経産大臣に抜擢された菅原一秀氏。一昨日、本サイトでは、2016年に「週刊文春」(文藝春秋)で元愛人からモラハラ被害を告発され、菅原氏が当時27歳だったこの元愛人に「女は25歳以下がいい。 25歳以上は女じゃない」と言い放った挙げ句、「子供を産んだら女じゃない」とまで言っていたという問題について取り上げたが、菅原氏をめぐってはカネの疑惑も取り沙汰されてきた。 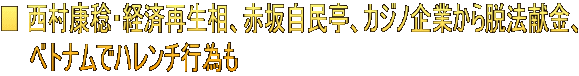 たとえば、2009年には、菅原氏が代表を務める政治団体が発注した高級メロンを、菅原氏の選挙区の有権者90人に贈っていたという公選法違反疑惑を朝日新聞が報道。 また、昨年12月にも、菅原氏の後援会が支援者などから会費を集めたバス旅行の収支を政治資金収支報告書に記載していなかったことが発覚。 後援会は収支報告書を訂正したというが、小渕優子経産相(当時)は後援会主催の観劇会の収支を不記載にしていたことなどが判明し辞任に追い込まれている。 しかも、菅原氏の後援会が収支を不記載にしていたのは2013〜15年、2017年と複数年にわたっており、悪質と言わざるを得ない。 さらに、菅原氏に輪をかけてひどいのが、内閣官房副長官から経済再生担当相に抜擢された“安倍首相の腰巾着”である西村康稔氏だ。 西村氏といえば、昨年の「平成最悪」となった豪雨時に例の「赤坂自民亭」に安倍首相と一緒に参加し宴会の模様を嬉々として投稿、〈笑笑 いいなあ自民党〉などと発信、その後は〈自衛隊員約21,000名が人命救助など活動中〉と拡散したが、これはデマで、2万1000人の自衛隊員は待機中にすぎなかったことが判明した件などが記憶に新しいが、忘れてはならないのが、2013年に「週刊文春」で報じられたベトナムで女性を買った疑惑だ。 記事によると、西村氏は2012年7月に出張先のベトナムでカラオケ・クラブから7人のホステスを宿泊するホテルのスイートルームに呼び入れ、その後、残った3人と行為におよび、対価としてあわせて600ドル弱を支払ったと、3人のうち2人の女性が証言。 このほかにもホテルでの目撃談をはじめ、複数の関係者がこの疑惑を裏付ける証言をおこなっている。 しかも、この疑惑を追っていた記者に対し、西村氏の私設秘書を名乗り、過去に恐喝未遂容疑で逮捕されたことのある人物が「記事を書けば恥をかくのはお前たちだ」と何度も〈恫喝めいた電話〉をかけてきたとも報じられた。 恫喝によって記事を潰そうとしたのが事実ならば、2重の意味で大臣としての資質などあるはずがない。 また、昨年7月には、米大手カジノ企業「シーザーズ・エンターテインメント」の日本進出におけるアドバイザーである人物が、西村氏をはじめとするカジノ議連所属の国会議員にパーティ券購入というかたちで資金提供していたと報道され、西村氏自身も国会で事実だと答弁。 つまり“脱法献金”を受けていたことを認めたのである。 凄まじい「タマネギ」っぷりの西村氏だが、安倍首相の側近といえば、総裁外交特別補佐を務め、今回、法務大臣に登用された河井克行氏も、元秘書の男性が2016年に傷害事件とパワハラ疑惑を「週刊文春」に証言している。 この男性は、1999年4〜7月に運転手を兼任するかたちで秘書を務めたが、「運転の仕方や言葉づかいが気にいらんと言っては、(河井氏が)『このやろう』と罵声を浴びせかけ、ハンドルを握る私の左腕めがけて後部座席から革靴のまま蹴ってきよるのです」と言い、そうした結果、全治14日間の大ケガを負ったと告発。 「週刊文春」には、当時、病院で撮影されたという写真も掲載、そこには左腕にアザがしっかりと写っている。また、河井氏に “対立候補のポスター剥がし”もやらされたとこの元秘書は証言しているのである。 しかも、河井氏の疑惑はこれだけにとどまらず、後追いした日刊ゲンダイの記事では、違う元秘書も「私も『国会議員の車の運転席の後ろが汚れてるのはなんでか知ってる? 蹴るためさ』と言われ、途端に恐ろしくなりました」とコメント。 河井氏の地元・広島の「第一タクシー」の会長までもが「うちは河井事務所から配車の要請があっても、一切お断りしています。 河井先生が乗務員の運転席を蹴るわ、人を人とも思わないような暴言を吐くからです。『もっと速く走れ!』と法定速度以上を出すよう要求され、危うくスピード違反に加担させられそうになった乗務員もいました。もうコリゴリですわ」と証言している。 元秘書への暴力や「ポスター剥がし」を命じた件などが事実であれば、河井氏が法務大臣を務めることに恐ろしささえ感じずにはいられないが、それは首相補佐官から農水大臣に抜擢された江藤拓氏も同じだ。 というのも、江藤氏は2016年、当時の森山裕農水相(現・自民党国会対策委員長)や西川公也・元農水相らとともに、TPP(環太平洋経済連携協定)交渉中だった2015年に一般社団法人「日本養鶏協会」(養鶏協)の会長から現金20万円を受け取っていたことが発覚。 養鶏協は国内向けのTPP対策予算を狙い、協会幹部からは「鶏卵業界に予算をもらうなら、政治家ともっと密接になったほうがいい」という声が出ていたというが(「週刊朝日」2016年7月15日号/朝日新聞出版)、こんなふうに農水族議員という立場で違法の可能性が高い献金・寄付を受けていた人物に、果たして農水大臣が務まるのか。 まだある。国家公安委員会委員長となった武田良太氏は、付き合いのあったプラント製造会社の会長に対し「インドネシアは、日本のODA(政府の途上国援助)枠がまだ9千何百億円か残っている。それを使って、プラントを売ることができますよ」などと語り、「(現地視察に)何人か議員を連れていくから、面倒を見なくちゃいけない。 いくらか用意してくれないか」と持ちかけていたことを「週刊朝日」2009年8月14日号が報道。この会長の証言によれば、視察直前に現金300万円、さらに赤坂の寿司店でも現金100万円を渡したが、「視察もその後、どうなったのかウヤムヤのまま」。 さらには〈武田氏の政治団体の政治資金収支報告書に、これらの記載は見当たらない〉というから、この会長の証言が事実であれば政治資金規正法違反にあたる行為だ。 また、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当相に抜擢された橋本聖子氏も、今年、白血病であることを公表した水泳の池江璃花子選手について、講演会で「池江選手が素晴らしい発信をしてくれたことによって、スポーツ界全体がそんなことで悩んでいるべきではない、ガバナンス、コンプライアンスで悩んでいる場合じゃない、もっと前向きにしっかりやりなさい、ということの発信を、池江選手を使って、私たちに叱咤激励をしてくれているとさえ思いました」 (朝日新聞デジタル2月16日付)と発言。 ようするに、池江選手を利用して「ガバナンスやコンプライアンスなんてどうでもいい」と言ってのけたのである。 さらに橋本氏は、ソチオリンピックの閉会式が終わった後に選手村でおこなわれた打ち上げパーティーでフィギュアスケートの高橋大輔選に抱きつき何度も強引にキスをしたと写真付きで「週刊文春」に報じられている。都合よく選手を政治利用し、権力を利用した悪質なパワハラ・セクハラまでおこなった人物を東京五輪・パラ担当相にしてしまうとは驚愕だ。 マルチ商法の広告塔にセクハラ、パワハラ、脱法献金、闇ガネにタカリ疑惑……。 そもそも、これら初入閣の大臣たちだけではなく、経産大臣から外務大臣に横滑りした茂木敏充氏は、昨年、公選法違反の“手帖配布”問題が持ち上がっており(詳しくは過去記事参照)、もはやこの安倍新内閣は “スキャンダル・疑惑のデパート”というべき状態なのだ。 だが、驚くべきは、このほかにも“危ない”大臣がいるということだ。 じつは、昨日、『羽鳥慎一モーニングショー』(テレビ朝日)に出演した田崎史郎氏が、「『この人いれちゃうの?』という人が3人くらい入っている」と言い、初入閣である田中和徳復興相と竹本直一科学技術担当相、北村誠吾地方創生担当相の名前を挙げたのだ。 田崎氏は「長く入れなかった人には、それなりの理由があるんです」と思わせぶりに語ったが、御用ジャーナリストの田崎氏でさえツッコまざるを得なかったということは、今後、この3人の疑惑・スキャンダルが出てくる可能性も多いに考えられるだろう。 しかし、問題はメディアの姿勢だ。ちょっと調べれば上記にあげてきたような疑惑・スキャンダルはすぐにわかるし、だいたい高市氏や加藤氏の再任や、加計学園問題のキーマンである萩生田光一氏をよりにもよって文科大臣に引き上げるという常軌を逸した人事は誰の目にもあきらか。だというのに、昨日のワイドショーはそうした問題にツッコミもせず、小泉進次郎の初入閣でお祭り騒ぎ状態に。 さらに、新閣僚の記者会見でも、これまでの疑惑やスキャンダルについて追及をおこなう質問はほとんど飛ぶことがなかった。安倍政権以前ならば、内閣改造後の新閣僚会見では記者が過去の疑惑やスキャンダルを洗い、それについて質問を浴びせることは普通におこなわれていた。 だが、そんな当たり前さえ、この国のメディアからは失われているのだ。 大臣の不正や疑惑が持ち上がっても追及もせず、「安倍総理は疑惑がある人を大臣なんかに任命しない」とまで言ってのける。こうした異常な状況があるからこそ、安倍首相は好き勝手に、問題議員たちを堂々と大臣に登用できるのだ。 メディアがこの体たらくでは、この「タマネギ内閣」の疑惑やスキャンダルが報じられることもないのだろう。 (編集部) 【出典】LITERA 2019.09.12 02:01
|
|---|
| 【出典】LITERA 2019.09.12 02:01 |
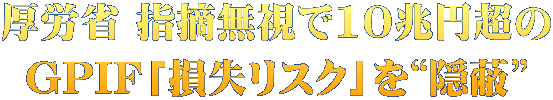 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
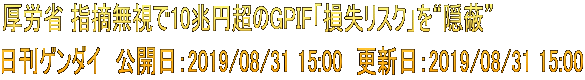 厚労省が公表した年金の財政検証で、楽観的なケースでも30年後に給付額が2割減少することが分かり、国民の不安は募るばかりだ。さらに30日、同省は給付額確保のための積立金運用に潜む損失リスクを“隠蔽”していたことまで発覚した。 年金保険料の一部を原資とした約160兆円の積立金を運用する厚労省所管の「年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)」。国内外の株式などで運用しているが、昨年10~12月期に14兆円の損失を出し問題となった。 GPIFはそんな最悪の場合を想定し、損失規模を事前に試算する「ストレステスト」を実施しているのだが、会計検査院にその結果を公表するよう求められていたにもかかわらず、同省はヒタ隠ししていたのだ。30日の野党ヒアリングで明らかになった。 検査院は今年4月に公表した報告書で、〈GPIFは、収益が減少するリスクについて国民に対して丁寧に説明を行っていく必要がある〉としたうえで、〈ストレステストの結果等中長期のリスクについて業務概況書に継続して記載することが重要〉と指摘。国民の年金を基に運用しているのだから、検査院の指摘はもっともだ。ところが、GPIFが7月5日に公表した概況書には、ストレステストの結果についての記載が一切ない。厚労省は検査院の指摘を「ガン無視」したというわけだ。 ヒアリングで追及された年金局資金運用課長は緊張した様子で、非公表の理由を「(金融)市場等への影響に留意した」と説明。一方、検査院の厚生労働検査第4課長は、厚労省の対応に不満があるのか「引き続き、GPIFと厚労省の対応状況を確認していく」と厳しい表情で話した。 「4月に国会で追及された根本厚労相は『ストレステストの結果を含め、概況書への記載を検討する』などと答弁していました。しかし、概況書公表は参院選公示の翌日で『2000万円不足』問題も連日報道されていた。GPIFのマイナスリスクを公表すれば、さらなる“年金不信”を招き、安倍自民に大打撃です。“忖度”した厚労省は結局、検査院の指摘を無視してでも、公表を避けたかったのでしょう」(永田町関係者) 同省は通常6月の財政検証公表も、今回は参院選後に先送りし、批判を受けている。そのうえ、GPIFの運用リスクまで“隠蔽”するとは。 「これまで、四半期単位で数兆~十数兆円の損失が出てきている。ストレステストの結果は、少なくとも10兆円規模のマイナスでもおかしくない」(厚労省担当記者) 経済ジャーナリストの荻原博子氏はこう言う。 「厚労省は昨年、14兆円もの損失を出したことをキチンと総括したようには見えません。身内である検査院の指摘まで無視したわけですから、国民の保険料を預かっているという意識が希薄なのでしょう。政権に忖度して情報を隠しているのなら、許されることではありません」 そもそも、国民の年金を“株ギャンブル”につぎ込んだこと自体が大きな過ちである。 【出典】日刊ゲンダイ 公開日:2019/08/31 15:00 更新日:2019/08/31 15:00
|
| 【出典】日刊ゲンダイ 公開日:2019/08/03 17:00 更新日:2019/08/03 17:00 |
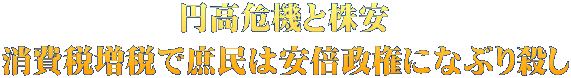 |
||||
|---|---|---|---|---|
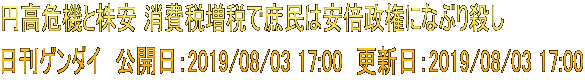 〈9月1日から、残りの3000億ドル(約32兆円)相当に10%の追加関税を課す〉 6月末に行われた、米国・トランプ大統領と中国・習近平国家主席との首脳会談以降、一時休戦状態となっていた米中貿易戦争が再び、ガチンコバトルに突入だ。トランプがおととい(1日)のツイッターで、中国からの輸入品ほぼすべてに制裁関税を拡大する「第4弾」を発動すると明らかにしたのだ。 米通商代表部(USTR)は5月に現在制裁対象から外れている3000億ドル分の中国製品3805品目に最大25%の関税を上乗せする案を発表しているが、今回の「第4弾」が発動されると、対中制裁の対象は実に計5500億ドルに達し、中国からの年間輸入実績に匹敵することになる。 トランプはまた、記者団に対し、貿易協議が決着するまで中国製品に関税をかけ続けるとし、税率25%超の引き上げも示唆。これに対し、中国もレアアース(希土類)の対米輸出規制を検討するなど、米中貿易戦争はさらなる長期化が避けられない見通しとなった。 これを受け、きのうの東京株式市場は、自動車など輸出関連銘柄を中心に全面安の展開となり、日経平均株価の終値は前日比453円83銭安の2万1087円16銭となり、外国為替市場では円高も進行した。
「自分ファースト」のトランプにとって米中貿易戦争がもたらす世界経済の行方など、どうでもいい。最大の関心は来年の大統領選で、選挙に勝つまで対中強硬姿勢を徹底的に貫くつもりだ。 仮に米中貿易戦争で米国経済がダメージを受けたとしても、金融緩和でしのげばいいと気楽に考えているのだろう。 そんなトランプに尻を叩かれた米連邦準備制度理事会(FRB)は、低失業率で過去最高値圏の株価を維持しているにもかかわらず、リーマン・ショック後の2008年12月以来、10年7カ月ぶりとなる政策金利の利下げを決定。 「トランプ・チャイルド」と揶揄されるパウエル議長は金融緩和の長期化を否定したものの年内に追加緩和を行う公算が高い。主要な中央銀行では欧州中央銀行(ECB)も9月に利下げを実施する方向で、今後、米欧に引っ張られる形で世界各国で利下げに踏み切る国が相次ぎ、金融緩和が激しさを増すことになる。 この影響をモロに受けるのが日本だろう。世界の中銀がそろって利下げに動けば、円高圧力は避けられない。当然、輸出企業の収益を圧迫するため、外需頼みだった日本経済は大打撃だ。日本も他国に追随して金融緩和すればいいが、そう簡単ではない。すでに黒田日銀はこの6年半、安倍政権のハリボテ経済政策「アベノミクス」を支えるため、「異次元緩和」と称して「利下げ」と「国債の買い入れ」を積極的に進めてきたからだ。 黒田日銀は7月末の金融政策決定会合で「ちゅうちょなく追加的な金融緩和措置」との声明文を公表したが、すでに“禁じ手”と言われる「マイナス金利政策」まで導入している状況で、これ以上、どんな緩和策を打つ余地があるのか。誰が見ても「打つ手なし」というのが実態だろう。 経済評論家の斎藤満氏はこう言う。 「トランプの対中関税発言は、FRBに次の利下げを暗に迫ったとみていい。おそらくFRBは9月に欧州と足並みをそろえて再利下げする可能性が高い。日銀も円高を避けるために対抗するでしょうが、国内の金融機関はこれまでの緩和策で収益が大幅に悪化するなど、すでに副作用が出ている。追加緩和すれば副作用が酷くなるだけ。金融業界も国民生活もメチャクチャになります」 世界経済の減速、金融緩和競争による円高進行、日米貿易協議での農産品の関税引き下げ圧力……。タダでさえ日本経済を取り巻く環境が厳しさを増す中、安倍政権が景気悪化に追い打ちを掛けるように強行するのが「狂気の愚策」とも言うべき、消費増税10%だ。 大体、すでに現時点で消費増税を行う環境にないのは明らかだ。2020年の東京五輪の会場建設やインフラ整備に伴う特需の限界が叫ばれ始め、黒田日銀の金融緩和が招いた不動産投機マネーによるバブル景気崩壊の懸念も指摘されている。 慢性的な人手不足は解消されず、実質賃金(5月)は前年同月を5カ月連続で下回るなど、経済にとって何ひとつ明るい材料がない。このまま消費増税を強行すれば庶民生活、経済は徹底的に破壊されてしまうだろう。 それでも何が何でも消費増税したい安倍政権は7月末の臨時閣議で、増税に伴う景気対策を別枠で扱うことを決定。すでに本年度予算で盛り込んだ2兆円規模の対策費に加え、年末に向けた予算編成でも新たな具体額を検討するという。 しかし、わざわざ数兆円規模の対策予算を組むのであれば、一体、何のための消費増税なのか。しかも「対策」とは言うものの、どれもケチな内容の絵に描いた餅。消費増税まで2カ月に迫る中、まるで普及していない。立正大客員教授の浦野広明氏(税法学)がこう言う。 「消費者にとっては8%だろうが、10%だろうが、消費税を含めて価格提示された通りに支払うだけですから、増税対策は何ら関係ありません。必然性が乏しい政策ですから、周知されず、普及しないのも当然です。『対策』と言えば、何か国民のために取り組んでいるかのように聞こえますが、投じられる税金はまったくのムダ遣いとしか思えません」 とりわけムダの極みが「軽減税率」と「キャッシュレス決済のポイント還元制度」に向けた対策だろう。軽減税率は飲食料品の購入や持ち帰り品が対象だが、店内で飲食した場合や酒類は対象外。8%と10%の両商品を取り扱う店や中小企業は、軽減税率に対応したシステムの導入、改修が必要とされる。 政府はシステム改修費などで原則4分の3を補助する支援策を用意しているが、6月末までの申請件数は約11・1万件と利用予想の3分の1超。ポイント還元は10月~来年6月末まで、クレジットカードなど現金以外で買い物をした場合に購入額の2~5%分をポイントで還元する仕組みだが、経産省によると、制度に参加した申込店舗は現時点で約24万店と参加可能な店舗の約1割にとどまる。 〈そもそも一体改革を進めるための消費増税のはずが、増税とセットで出てくるのは景気対策しかない。本当に景気が刺激されればまだいいが、キャッシュレス決済によるポイント還元策では難しい。お客さまの買う場所が変わるだけで、買い物が増えるとも思えない。将来への不安は変わらないから、還元分は貯金に回るだろう〉 〈(ポイント還元の)効果は一切ない。むしろ、これまで経験したことのないようなポイント合戦や価格競争につながるだろう〉 日本食糧新聞の特別インタビュー(7月27日付)で、日本スーパーマーケット協会会長の川野幸夫ヤオコー会長は消費増税に伴う政府対策をこう切り捨てていたが、これがまっとうな経営者の見方だ。 川野会長はまた、〈政治に対する発言力について、今回ほど無力感を覚えたことはない。私たちの声はあまりにも取り上げられず、検討されることもない〉と憤っていたが、庶民も同じ。このまま安倍暴政を黙って眺めていたらなぶり殺し状態になるのは間違いない。 政治評論家の本澤二郎氏がこう言う。 「黒田日銀の6年半でハッキリしたのは、金融政策で経済をコントロールするのは不可能だということ。むしろ、その金融政策によって日本経済を悪化させてしまった。その上、消費増税など、とんでもない。経済の底が抜けてしまいます」 一刻も早く退陣させないと国民生活はズタズタにされてしまう。 【出典】日刊ゲンダイ 公開日:2019/08/03 17:00 更新日:2019/08/03 17:00 |
| 【出典】日刊ゲンダイ 公開日:2019/08/03 17:00 更新日:2019/08/03 17:00 |
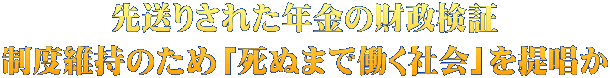 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
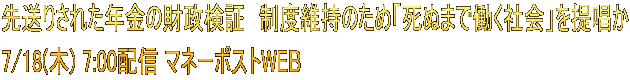 金融庁が6月にまとめた報告書で、年金だけでは老後資金が2000万円不足すると指摘されたことで、年金制度への不安が高まっている。今後の年金制度はどうなっていくのか。経済アナリストの森永卓郎氏は、政府・厚生労働省が目論む年金制度の将来と、高齢者の生活がどうなるかについて、次のように展望する。 * * * 政府はすでに、このままでは年金制度が立ちいかなくなることがわかっていたため、「一億総活躍社会」という謳い文句のもと、「みんな70歳まで働け!」という方針を押し進めている。 たとえば、2014年に行なわれた公的年金の将来見通しを試算した厚生労働省の財政検証では、高齢者の労働市場への参加が進むケースとして、2030年の65~69歳男性の労働力率を67%と想定し、そうなれば現行水準並みの年金給付が維持できると結論づけた。 この試算が意味するのは、3分の2の男性が70歳まで働き続け、年金保険料を払い続けることが、年金制度の崩壊を免れるための絶対条件ということである。逆にいえば、それが実現できなければ、所得代替率(厚生年金収入の現役世代の手取り収入に対する割合)50%以上の年金給付は維持できなくなるということだ。 2019年は5年に1度の財政検証の年だ。その新しい財政検証の結果はすでに出ているが、参議院選挙を考慮してか、今はまだその内容が隠されている。参院選後に公表を延ばしたこと自体、国民にとって相当厳しい内容であることは想像に難くない。 おそらく、65~69歳男性の労働力率は70.1%、65~69歳女性の労働力率も53%台に設定され、それなら所得代替率50%以上を維持できる。すなわち、「みんな死ぬまで働け!」という結論になるのは間違いないだろうろう。 これらが象徴するように、政府は今、年金制度維持のために給付期間を短縮することで帳尻を合わせようと躍起になっている。 現在の年金支給開始年齢は原則65歳だが、受給開始を60歳から70歳の間で自由に選べる制度となっている。それを75歳まで繰り延べて選択可能にするというのが、政府の次の一手だ。 そして、年金受給を繰り下げれば割増しとなって受給額が増えると謳って、事実上70歳代から受給を開始する人を増やしていく。そのうえで、「みんながそうしているのだから」という機運を高めて、最終的に支給開始年齢自体を原則70歳に繰り延べすることを狙っている。 現在、65歳時点の男性の平均余命は17年だ。支給開始を原則70歳にすれば、男性の平均受給期間は17年から12年に減り、3割カットできることになる。それなら年金制度はギリギリ崩壊せずに済むというのが政府の思惑なのだ。 しかし、このまま政府の目論見通りになったら、国民の老後はどうなるのか。男性の健康寿命は72歳である。70歳まで働いてようやく年金をもらえるようになり、これから悠々自適の老後が送れると思っても、わずか2年後には介護施設などに入所しなければならなくなる人が大半となる。そんな老後で本当に幸せだろうか。 【出典】7/18(木) 7:00配信 マネーポストWEB
|
| 【出典】LITERA 2019.07.15 12:22 |